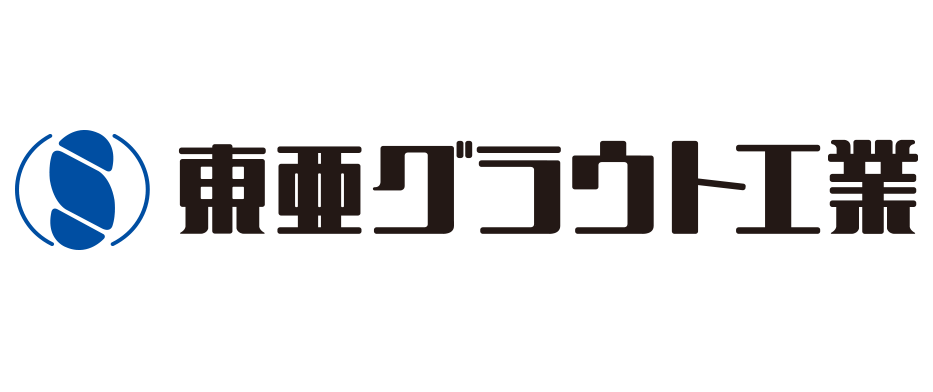企業は今、自社工場での排水処理や水再利用など、自社の水だけではなく、国外も含めたサプライチェーン全体、商品の使用や廃棄段階における水、さらには水に関する人材育成や水を通した地域貢献などにも取り組むようになっています。
その背景には洪水や渇水などのリスク拡大、海外では人口増加や新興国の経済発展に伴う水資源の悪化や不足、投資家の評価基準の変化などが挙げられます。
企業と水との関係性は以前から重視されていますが、それが今、大きく変化しつつあります。その変化の現在地点を明らかにし、これからの企業の価値を水からいかに創造するのかなどについて、水について先進的に取り組んでいる花王、サントリー、三菱地所の担当者の方々に議論していただきました。(進行役:Water-n代表理事 奥田早希子)
※3回連載の2回目
参加者

花王 ESG活動推進部長

サントリーホールディングス サステナビリティ経営推進本部 部長

三菱地所 サステナビリティ推進部 事業主任

三菱地所 エリアマネジメント企画部・サステナビリティ推進部 マネージャー
話題3 「水」で選ばれる企業・商品
- 坂村氏 水景で居心地のいい空間を創る
- 高橋氏 性能×環境×楽しさのバランスを
――サントリーさんは「サントリー天然水」で「ウォーター・ポジティブ」プロモーションをはじめられたそうですが、その前後で消費者行動の変化を感じますか。
瀬田氏 より若い世代にメッセージを伝えたいと考えていた中で、20代から30代前半の世代への理解が広まっているという手ごたえを感じています。
若い世代に訴求するために、「取水量以上の水を水系に育む」というメッセージとセットでブランドストーリーを語ることを重視しました。水は工場で詰めますが、その水は工場が汲み上げる地下水の水源涵養域にある森が育んでいます。サントリーは自然の恵みの一部を頂戴し、 ボトルに詰めて、生活者にお届けしている。だからこそ、僭越ながら使わせていただいた分の水をしっかりとお返ししていく。このサントリーの考え方や取り組みをストーリーとしてお客様にお伝えすることが、ブランド価値を高めることにつながったと感じています。
そこに気候変動という社会課題が加わると、「サントリー天然水」のブランドイメージを構築する上で、もう1つ別の訴求ポイントが見えてきます。それは、「サントリー天然水」が洪水や災害時の社会インフラになっているということです。備蓄飲料として供給を途絶えさせてはいけない、という製造者責任への要請が強くなってきたと感じます。それも踏まえて、工場での水の生産の持続性だけではなく、流域全体での水マネジメント、地下水の涵養まで含めてお客様に訴求していきたいと思います。
――「ウォーター・ポジティブ」コミュニケーションで、電車のジャック広告をされていますよね(写真2)。キティちゃんのかわいいポスターが印象的です。先日、そのポスターを見た小学生の女の子が「見て見て、ウォーター・ポジティブだよ」とお母さんに嬉しそうに話しているのを見かけ、商品への共感が生まれていると感じました。
瀬田氏 それはうれしいですね。

――そうはいっても生活者としては値段も気になります。ウォーター・ポジティブのメッセージが届き、高くても選ぶという人も増えていますか。
瀬田さん 緒に就いたばかりの取り組みなので、まだそこまでの変化を確認できていませんが、しっかりとブラントストーリーとして伝えることで、持続可能性への取り組みを、それこそポジティブにとらえてもらえるとありがたいです。
――高橋さんはそのような生活者の行動変容を感じる時はありますか。
高橋氏 洗浄剤はやはり洗浄性能が基本なので、環境のために性能を犠牲にしてまで買おうというお客さんはいないと思います。洗浄プラスアルファの驚きが必要だと思います。
例えば2回のすすぎが1回に減らせる衣料用洗剤「アタック」は、基本の洗浄力や利便性に加えて、水の使用量を減らせたり、環境に配慮した界面活性剤を使用したりしていることを伝えて初めて「だったら買おう」と行動が変わります。基本は性能や驚きの価値で商品が選ばれますが、花王の商品を使用することで、社会も、地球にも良いことに繋がるということを伝えることが重要ですね。
――不動産の場合はいかがでしょうか。選ばれるビルにはどのような条件があるのでしょうか。
坂村氏 安全であることは基本ラインです。それ以上に緑や木があって、木陰に座りお弁当を食べられるような居心地の良い空間は、ビルで働く方や来街者をとても惹きつけます。環境面だけではなく、町おこし的なイベントもやりますし、そうしたまち全体の営みを見て選んでいただければうれしいです。
――居心地がいい雰囲気、来た人も楽しめるまちというのは訪れたくなりますね。
高橋氏 「楽しい」ということは大事ですね。そのことに最近、商品を通して気づかされました。
食器用洗剤「キュキュット」です。2023年に、使用後にその容器をペコっと楽につぶせる「未来にecoペコボトル」に変更したところ、ペコっという感触が楽しいとウケたんです。実はこの容器はプラスチック使用量を減らした容器なのですが、「プラスチックの量を減らしました」とだけ伝えたら「いいね」で終わったと思います。
性能、サステナビリティ、そして楽しさ。これらがバランス良くストーリーで伝えられるといいですね。
――最近はモノ消費からコト消費に代わり、体験にお金を払う人が増えています。容器をペコっとする楽しい体験も、まさにコト消費の流れに即していると言えそうです。
高橋氏 家庭用のゴミの分別も、楽しさの要素が入ればもっと進むのかもしれません。
坂村氏 ビルでは毎日、大量の廃棄物が出され、あまり分別されていない実態があったのですが、それはビル室内のゴミが、徹底して分別して集める仕組みになっていないからだと気づき、分別回収できるゴミステーションへの改修を進めています。
テナントの方々にも細かく分別してもらえるよう協力をお願いしていますが、「燃えるゴミ」用のゴミ箱があると、纏めてそこに入れてしまわれることもあるので、「燃やさざるを得ないゴミ」と書くなど工夫しています。
――それは楽しい表記ですね。企画側も楽しむことが大切です。とはいえテナントの方々は手間が増えますから、不評の声もあるのではないですか。
坂村氏 それはありますね。ですから弁当ガラは洗わずに捨ててもいいルールにして、少しでも手間を減らすようにしています。リサイクルするには工場での洗浄が必要となり、その分だけゴミの引き取り価格は高くなるのですが、そこは受容しています。
松井氏 各ビルのゴミステーションがビルの地下にあって、そこが暑くて生ごみなどが腐ると臭くなる。各テナントのゴミ当番の人はそこから一刻も早く立ち去りたくて、分別どころではなく、ゴミ袋を放り投げていってしまう人が多かったんです。
ですから、早く出たいと思わないような空間、しっかりと分別できる空間にしようということで、カラフルなデザインでどこに何を捨てればいいかを分かりやすく伝えたり、多言語化も進めています。
瀬田氏 当社では2030年までにすべてのペットボトルをリサイクル素材や植物由来素材等に100%切り替え、化石由来原料の新規使用をゼロにする目標を掲げています。それを実現するうえで、三菱地所さんのような事業系資源を排出する企業様との連携は重要で、今後も広げていきたいです。一方で生活者からの回収量を増やすために、ペットボトルはゴミではなく資源であることを伝える、「ボトルは資源」というロゴをペットボトル商品パッケージに掲載しています。資源としてきれいに洗って分別してもらえるようにメッセージを出しています。
――洗剤も、ペットボトル水も、まちも、使う人が一緒に取り組むことで、持続可能性という価値を高めることができるということですね。
高橋氏 花王の工場では、設備の加熱などユーティリティに使う水はリサイクルしたり、別の用途にカスケード利用したりして水使用量を削減する取り組みをしていますが、それでも工場で使う水は全体の1割。残りの9割が、商品の使用段階で使う家庭の水です。だからこそ使う人の行動変容は欠かせません。
家庭内では特に洗浄に使う水が多い。それを減らすために、衣料用洗剤ではすすぎ2回を1回に減らしたり、シャンプーや食器用洗剤は泡切れの良い商品を開発しています(写真3)。

洗浄するには泡立ちが良いほうがいいのですが、使った後は泡切れが良いほうがいい。でないと排水口にいつまでも残る泡を流すために、水を流し続けなければなりませんからね。泡立ちが良く、泡切れもいい。この相反する要望を両立できる商品には、実は高い技術力が詰まっているのです。
水を減らせば水道代も減り、電気代も節約できるし、CO2も削減できます。それらを伝えながら、水を大切に使っていただきたいと思います。

「環境新聞」(2025年1月15日発行号)からご厚意により転載させていただいております
この回では、新聞紙面ではスペースに制限があって割愛せざるを得なかった内容もすべてお伝えしています。ぜひ、ご一読ください。