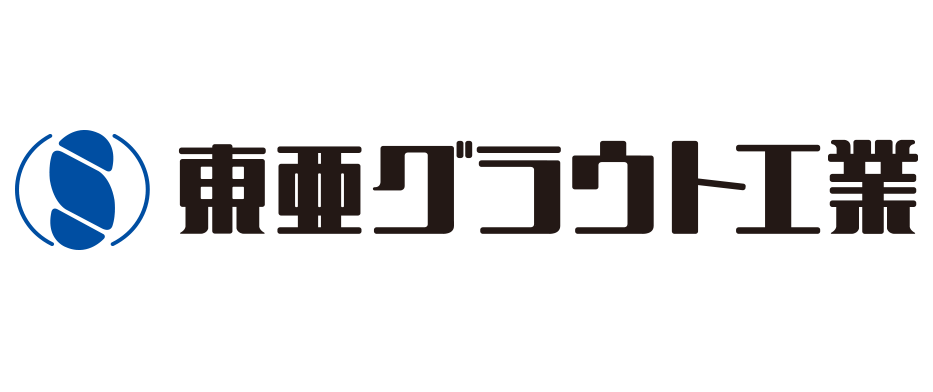2025年4月12日から6日間にわたって渋谷ヒカリエで「Deathフェス」なるイベントが開催されていた。その名の通り「死」をテーマとして、今をどう生きるかを考えるのが趣旨である。
知り合いで日本タナトフォビア協会会長の浦出美緒さんが14日にワークショップ「学び×死 生と死の学校 平均的な人はいない~死があなたをあなたらしくする~」を主催されたので参加してきた。
※日本タナトフォビア協会:タナトフォビア(死恐怖症)についての社会的認知向上を図り、タナトフォビアを抱える人々やその家族にサポートを提供することを目的とした団体
Deathフェスの社会背景として、多くの人が死んでいく「多死社会」という日本ならではの現実がある。同フェス事務局によると、日本では2023年の年間死者数は過去最多の157万人で、40年前の2.2倍だという。
一方、インフラも老朽化が進み「インフラ多死社会」を迎えようとしている。だから「インフラ多死社会」にどう向き合い、乗り越えていくのか、そのヒントがあるかもしれない。と、失礼ながらかなり小さな期待を持って参加した。しかし、参加してみて予想が大きく外れた。いい意味で、だ。人類の「多死社会」への向き合い方には、「インフラ多死社会」と向き合うヒントがふんだんに散りばめられていた。
その全体像が大きな布のように編み込まれたものとすれば、ここでは短い糸くらいしか紹介できなくて歯がゆいが、当日、ファシリテーターを務めた元禅僧で哲学コミュニケーターである大角康さんの言葉をいくつか紹介し、私なりにインフラに当てはめて考えみた。「インフラ多死社会」を乗り越えるヒントになればうれしい。なお、大角さんの今回のワークショップでは、哲学者であるマルティン・ハイデッガーの思想が取り上げられている。

■大角さんの言葉(筆者なりにまとめたものである)
平均的でない(偏りがある、個性がある)ことが普通であるが、ヒトは個性を自ら消したがる。それは、偏りがない(個性がない、世間になじむ)ほど世界は安定し、偏りがない人を良しとするから。この場合、「良し」とする自己肯定の根拠が外から与えられているので、それを守ることで安心できる。
しかし、自分にとって「良し」とは何か、と考え始めると、それまで外から与えられていた自己肯定の根拠を見失い、不安になる。
自己肯定の根拠を見失って不安になるが、その不安に飲まれずに自分らしい偏り(個性)を生きたいなら「死と向き合え!」。死を見つめることは今を生きることである。
■インフラに当てはめてみる
これまでのインフラは、日本全国、同じ設計基準や構造基準、目的によって一律(偏りがない、個性がない)で整備されてきた。この場合、それら基準通りに整備すれば「良し」とする根拠が国から与えられているので、実際に事業を手掛ける自治体や民間企業はその根拠を守ることで安心できた。
しかし、インフラの整備が一巡した今、自治体ごとにインフラの老朽化度合いや、インフラを使う人口の減り具合、地域ごとに抱える課題が異なっている。国が掲げる1本の御旗、1つの基準だけではすべての課題が解決できない。
だから今、地域にとって「良し」とは何か、多くの地域がその答えを探している。しかし、そこには外から与えられた自己肯定の根拠がないから、何をすれば「良し」なのか確信を持てず、不安に感じる自治体が少なからずあるのだろう。
地域独自の偏り(個性)を「良し」と肯定できるのは、地域でしかない。インフラを取り巻く地域らしい偏り(個性)を地域づくりに生かしたいなら「インフラの死と向き合うこと」。インフラの死を見つめることが、今のインフラを考えることである。
驚くことにインフラの整備時代には、作ったインフラは壊れないと思われていたという。そんなことがあり得ないことを、今、私たちは知っている。インフラにも死がある。その厳然たる現実に向き合うことができたからこそ、今あるインフラに向き合うことができている。
インフラには「死」がある。そして、おそらく、国にも都道府県にも市町村にも地域にも「死」がある。その「死」と向き合うことを止めてはならない。
(編集長:奥田早希子)