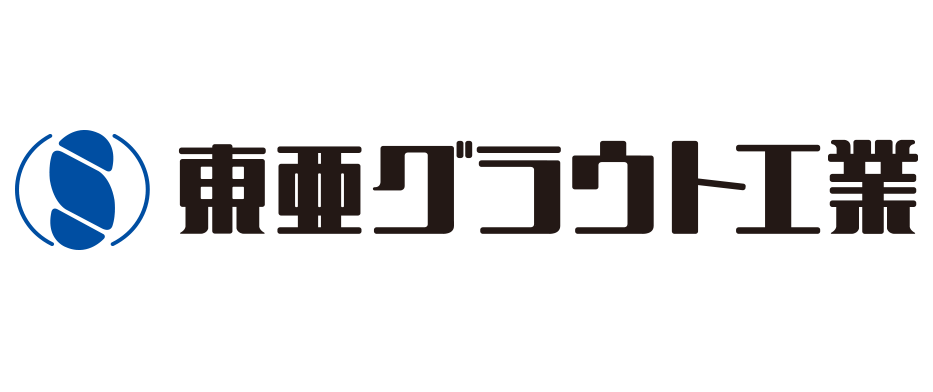企業は今、自社工場での排水処理や水再利用など、自社の水だけではなく、国外も含めたサプライチェーン全体、商品の使用や廃棄段階における水、さらには水に関する人材育成や水を通した地域貢献などにも取り組むようになっています。
その背景には洪水や渇水などのリスク拡大、海外では人口増加や新興国の経済発展に伴う水資源の悪化や不足、投資家の評価基準の変化などが挙げられます。
企業と水との関係性は以前から重視されていますが、それが今、大きく変化しつつあります。その変化の現在地点を明らかにし、これからの企業の価値を水からいかに創造するのかなどについて、水について先進的に取り組んでいる花王、サントリー、三菱地所の担当者の方々に議論していただきました。(進行役:Water-n代表理事 奥田早希子)
※3回連載の3回目
参加者

花王 ESG活動推進部長

サントリーホールディングス サステナビリティ経営推進本部 部長

三菱地所 サステナビリティ推進部 事業主任

三菱地所 エリアマネジメント企画部・サステナビリティ推進部 マネージャー
話題4 持続可能な水と企業
- 高橋氏 「せつない水の物語」でメッセージを発信
- 松井氏 水を守るために上流の森でネイチャーポジティブに取り組む
――水に関する取り組みの最新事例をお聞かせください。
松井氏 先ほどもお話したように、皇居の内濠が閉鎖性水系になって水質が悪化したことをうけ、環境省や国土交通省等を含めた官民連携で対策が検討されました。当社はその一環として、大手門タワー・ENEOSビル に、民間事業者としては初となる濠水貯留浄化施設を設置しました。
内濠の日比谷側に環境省の浄化施設があるのですが、水位が低下した時は使えません。そこで水位が下がった時に貯留施設から放水し、水位を上げて施設が稼働を続けられるような取り組みも実施しています。合わせて、当施設自体にも浄化機能があり、年間でおおよそ内濠の水一杯分を浄化できる機能を持っています。
また、水質悪化等に伴って危機に瀕している水草の再生にも取り組んでいます。皇居からいなくなってしまった水草も、もしかするとお濠の泥の中ではその種子がかろうじて生きている可能性があったため、エリアのワーカーさんと一緒に泥土を採取して(写真4)、ホトリア広場等の施設で培養して保全する活動を続けています。

その結果、これまでに失われたと思われていた6種類の水草を再生することができました。
一方、大丸有エリアは高層ビルが多く、そこだけでの取り組みには限界があるので、流域的な視点から関東圏の最上流である群馬県みなかみ町で「みなかみから始まるネイチャーポジティブプロジェクト」に取り組んでいます。水源涵養機能を確保するため、人工林を自然林に転換したり、ニホンジカが増えすぎないように取り組んだりしています。
――水源涵養機能を維持することに、ニホンジカが関係するのですね。
瀬田氏 ニホンジカは重要な課題です。当社の水源涵養林でも、鹿の頭数を管理したり、鹿柵を設置したりしています。鹿の打ち手(猟師)さんが高齢化している中、いかに打ち手さんと連携するかは難しく、どこの自治体も抱える問題です。
しかも、鹿は狩猟の仕方次第では、生息域が拡がっていってしまう。隣町との広域連携が重要ですが、行政区を超えた連携構築にも課題があります。
――水を考えると、鹿を経由して、猟師さんの高齢化問題にまでつながるとは驚きです。
瀬田氏 水を守るには、土を守る必要があります。日本では国土の3分の2が森林に覆われ、険しい山も多い。森林は降った雨を蓄え、地下水の流れを生み出し、川にも水を供給する。地下水が川に豊富な水を供給するから、夏でも平野部でも水が枯れない。そういう国土を守るには、森林で降った雨を浸透する機能が必要で、それを担うのが土です。
その土も、傾斜がきつい山で守るものがなければ、雨で流れてしまいます。それを防ぐのが地下に根を張る樹木であり、背の低い下草です。しかし、それを鹿がことごとく食べてしまいます。そうすると水を浸透する機能を持つ土壌が流され、水は蓄えられません。
松井氏 実は私は前職では、実際にニホンジカを捕獲するなど、みなかみ町で鹿の問題に取り組んでいたこともあります。
――そうなんですね!水を考えると、生物多様性や流域などに視点が広がり、同時に関係する人の輪も広がっていく。それだけ多様な人が自分事として関われる楽しさがあるということだと感じます。
高橋氏 水は生き物ではないので、生物多様性と結び付けられることに最初は違和感がありましたが、水循環の全体を考えることで生物多様性との関係性に気づくことができました。
瀬田氏 当社のバリューチェーンの上流は地下水ですが、実はその先に森林の土壌があり、さらにその先に土壌を育む植生や生き物がいる。その生態系がバリューチェーンの最上流であるという考え方を、浸透させていきたいと思っています。
――次に高橋さんから、花王さんの最新事例をお聞かせください。
高橋氏 当社に関係する水の9割が生活者から出ており、引き続き節水製品や、水の量を減らした濃縮製品の普及に努めていきます。日本では花王の商品を使うことで、およそ5億立法mの水を減らすことができました。もしも世界中で使っていただければ、効果は120億立法mに及びます。
花王の商品を使っていただくことで、環境に貢献ができるということをサイエンスベースで伝えたい。そして世界に広げていきたいです。
――続いて瀬田さんから、サントリーさんの最新の取り組みをお聞かせください。
瀬田氏 「環境目標2030」には、「水」の取り組みとして「水の啓発・安全な水の提供」を掲げています。
水の啓発に関しては、小学校の中高学年を対象に次世代環境教育「水育」を実施しています。2004年に日本で始まり、これまでに世界8カ国で計58万人超に水の大切さを伝えてきました。ベトナムでは日本の文部科学省にあたる教育訓練省が協力してくださり、教員への教育を通して毎年数十万人規模の子どもたちに「水育」を提供する機会をいただいています(写真5)。

安全な水の提供に関しては、安全な飲み水にアクセスできていない地域の小学校などにインフラを提供しています。
2030年までの目標として掲げていた双方合わせて100万人を2023年に前倒しで達成できましたので、目標を500万人に引き上げたところです。
そのほか、東京大学の沖大幹先生との共同研究で、淡水資源の時間的・空間的な偏在も考慮して企業の水リスクや水環境に及ぼす影響を評価するツール「ウォーターセキュリティコンパス」を開発して公開しています。水リスクを評価するために、多くの企業に活用していただきです。
――皆さんの取り組みは、単なるCSR活動にとどまっていません。なぜ投資をしてまで、そこまでやるのでしょうか。
瀬田氏 自社バリューチェーンの中での水の持続性を担保するために、工場の節水、「サントリー 天然水の森」などの水源涵養、原料の生産地の水使用効率改善、啓発活動の4つを重視しています。
一方、自社のバリューチェーンの外では、官や民、市民社会、NGOやNPOなどの活動に貢献できる部分もある。その貢献の形を主導的に作っていくことで、当社の水理念が世界に広がり、結果的に自社バリューチェーンにも効果を発揮する。そういう2つの戦略をとることで、おっしゃるようにCSRではなく、経営の一部として取り組んでいます。
高橋氏 パーパスの「豊かな共生社会の実現」に表されているように、企業の成長と、自然を守ることは、別物ではありません。むしろ自然を守ることに取り組まなければ、企業の存続どころか、人間社会として生き残れない時代になっていると感じます。
企業さえよければいい、という発想はあり得ません。それではいずれ自分の首を絞めます。社会全体のコストミニマムに向けて、企業の成長と環境を両立させるべきです。そのことには生活者も気づき始めており、一緒にやっていこうという流れがあります。
その流れを後押しするため「もったいないを、ほっとけない。」というコミュニケーションを展開しており、最近はその一環として「せつない水の物語」というメッセージも発信しています(写真6)。第一話は「その水は、シャワーの先からポタポタ垂れるお湯として流れていった。」です。今は第14話まであり、水を大切にしましょうというメッセージを伝えています。こうして流しっぱなしをやめましょうというメッセージを発信し続けることは大切だと思います。

瀬田さん あのメッセージには共感しました。
松井氏 2030年に向けた中期経営計画では、株主価値と社会価値の向上戦略を両輪に据えています。やはり、事業と社会は相互に作用しているという認識が背景にあります。
先ほど紹介したみなかみ町には当社の事業地があるわけではありませんが、広く考えればコアエリアである大丸有とは流域で繋がっています。その流域の最上流部ですから、事業地と関わる場所であると捉えています。
話題5 水からの価値創造
- 坂村氏 競合他社も仲間。みんなで取り組もう
- 瀬田氏 流域全体をまとめる仕組みが必要
- 高橋氏 すべての関係者と手を携えることがカギに
――最後に、水から企業価値を向上するために、これから取り組んでいきたいことをお聞かせください。
高橋氏 渇水地域にある工場では、周辺の方を含めたサスティナブルな取り組みが望まれています。ここは今後のチャレンジです。これからも商品を通して顧客価値の向上と、社会課題の同時解決に貢献していきたいです。
坂村氏 「三菱三綱領」に表されているように、岩崎小彌太の時代から、会社だけが良ければいいものではない、平等性が必要であり、社会に貢献し、生きていくというDNAが三菱グループには伝えられてきました。
先程も話題に上がったCSR活動にしても、事業に影響のない範囲で社会貢献するというイメージがありますが、それではもう地球環境は守れません。事業を通じて社会に貢献することで企業価値が高まる、と考えられない企業の生き残りは難しいと思います。
私たちは有機物を食べて生きています。いくらお金を儲けても、それは食べられないんです。自然の恵みが無くなれば、お金がいくらあっても生きていけない。今はかなり追い込まれた状況にあると思います。
そこを乗り越えるためには、みんなでやることが大事です。だから他のデベロッパーとは、サステナビリティの推進に関し頻繁に情報交換をしています。
大丸有に皇居から生物が飛来したら、ぜひ日本橋や渋谷まで飛んでいってほしい。ライバルではなく仲間なんです。
瀬田氏 当社の工場の敷地周辺や、原料の耕作地といった特定の場所を守るだけでは立ちいかなくなっています。仮に当社が「環境目標2030」を達成できたとしても、流域やランドスケープなど広大な土地の中で見れば与えるインパクトは大きくはありません。
ですから同じ流域で水を使う他のユーザーや企業、自治体と連携して、1つの目標を共有して、一緒に取り組む必要性を感じます。そうした関係者をまとめていく仕組みづくりが今後の課題と考えています。
高橋氏 皆さんがおっしゃる通りで、自社だけでの取り組みには限界があります。その認識があるからこそ、水では流域管理という考え方が求められたり、気候変動でも、自社努力だけでなく、自社が直接関与しないスコープ3での推進も求められたりしているのです。これからは流域に関連するすべてのステークホルダーと手を携えることがキーになると思います。
――本日はありがとうございました。

「環境新聞」(2025年1月15日発行号)からご厚意により転載させていただいております