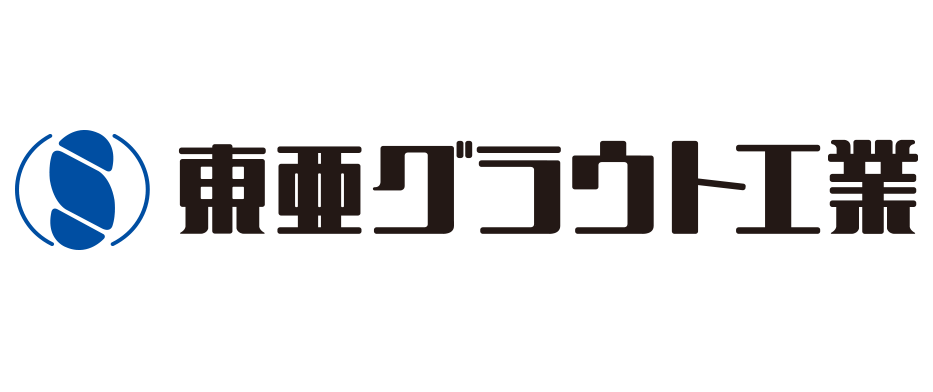ヴェオリア・ジャパン グループの西原環境など6社で構成するJVは、千葉県木更津市の下水汚泥を活用して水稲栽培用の混合肥料の製造・販売に乗り出した。10年以内に混合肥料の全量と、混合肥料で育てたコメの全量を、市内・近隣地域で流通させる「地産地消」の実現を目指す。
2025年4月1日、千葉県木更津市と下水汚泥堆肥化施設整備事業の設計・建設契約を締結した。ヴェオリア・ジャパン グループは日本では下水汚泥を肥料化する設備を建設した実績はあるが、設備の運営から肥料の流通までを手掛けるのは国内初となる。

混合肥料が売れ残って同市が在庫を抱えるリスクを回避するため、JVが全量を同市から買い取ってから肥料メーカーに転売する。
また、下水汚泥から作った肥料で育ったコメには重金属が含まれることへの懸念や、なんとなく不衛生に感じて消費者から避けられる恐れがあり、混合肥料を使いたがらない農家が出る可能性がある。そのため、大学で土壌中の重金属を長期モニタリングし、さらに(試験栽培した)コメも全量を買い取ることで、安心して混合肥料を使える環境を農家に提供する。
※( )内は2025年4月23日追記しました
同市はこれまで下水汚泥を、委託費と運搬費を合わせて年間1億5000万円かけてセメント原料として再利用していた。単純計算すると、本事業の運営期間である20年間で30億円となる。
一方、本事業では設備の建設費(約27億円)と、20年間の運営・維持管理の委託費(約21億円)を合わせて約48億円となる。
一見すると従来よりコストアップするように思えるが、同市の調査によると下水汚泥が今後20年間で現状の6500トンから8650トンまで増加するうえ、さらに燃料費や人件費の高騰も高騰する。これらを勘案すると20年間で51.7億円まで処理費用が増加すると見込まれることから、肥料化の方が費用対効果が高いと判断した。
事業概要
事業の概要と目的
目的
– 下水汚泥の全量を有効利用し、未利用資源を堆肥として地域農業に活用
– 「オーガニックなまちづくり」の実現
場所:木更津市潮浜の下水処理場内
期間:2025年4月1日〜2047年3月31日(2027年4月1日竣工式)
処理量:年間8,650.5トン(脱水汚泥)
総事業費:48億円超(設計・建設27億円、運営・維持管理21億円)
施設の特徴と運営方針
堆肥化の流れ
1. 脱水汚泥を木質バイオマスや廃白土と混合。
2. 一次・二次発酵を経て高品質なコンポストに加工(約6週間)。
3. 太陽光発電も併設(年間13.5万kWh発電)で脱炭素にも貢献。
品質管理と安全対策
– ロット単位で品質・重金属検査。
– トレーサビリティ導入により製造〜流通を一元管理。
地域との連携と社会的価値
地元との協働
– 地元企業(六幸電機、佐々木工務店、谷中造園土木)がJVに参画、地元雇用も推進。
– 肥料利用促進へ「木更津コンポスト利用拡大チーム」設立。市内サッカークラブ、ホテルなどが参加
– 10年以内に市内及び近隣地域での流通100%を目指す
– 「木更津ブランド肥料」の開発。
きさらづ地域循環共生圏の推進
– 教育、観光、農業など多分野に波及。
– ふるさと納税や災害対応にも貢献。
エコファクトリーとしての価値変換
従来の「下水処理場」から、資源を循環・再利用する「エコファクトリー」へと進化させる
【下水処理】
– 有害物質を環境に排出しないよう衛生処理。
– 環境に影響する成分を監視し、自然とのバランスを保持。
【水の再利用・リサイクル】
– 汚泥を脱水して品質を監視。
– 下水汚泥を肥料やバイオ燃料に転換。
– 再生水の利用先・方法の多様化を模索。
【エネルギー削減と脱炭素】
– バイオガスによるエネルギー生成。
– データ管理・自動制御で運転効率を最適化。
– エコ薬品の活用で薬品使用を最小化。
【地域・環境への貢献】
– 教育・雇用・生物多様性に貢献。
– 規制を遵守し、地域と連携した取り組みを展開。
まとめ:「つくる・つなげる・ひろめる」
– つくる:安全・安心・高品質なコンポスト製造と脱炭素。
– つなげる:地域と連携し肥料利用を促進。
– ひろめる:「エコファクトリー」モデルとして広く発信、オーガニックシティ木更津のブランド向上を目指す。