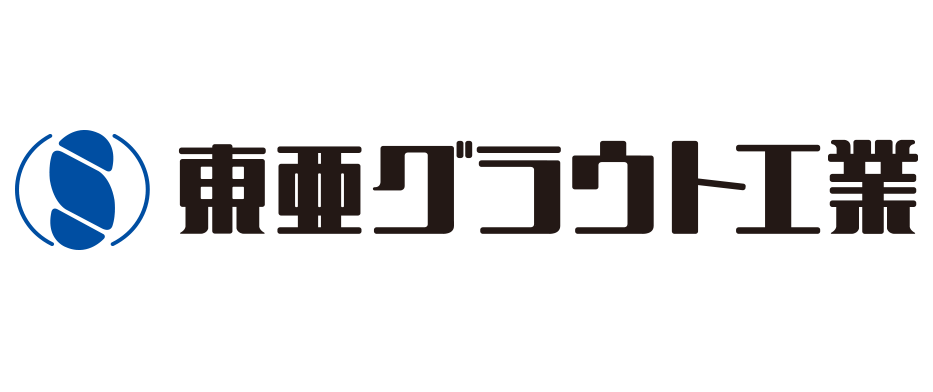日本で唯一、PPP(Public Private Partnership)の理論を学べる社会人大学院である東洋大学経済学研究科公民連携専攻の初代専攻長を務めた根本祐二教授が2025年3月に退官を迎えた。PPPの理論構築やPPPを実践する人材育成、日本におけるPPPの普及に尽力し、インフラの老朽化、更新投資の増大にいち早く警鐘を鳴らすなど多くの功績を残した。3月22日に同大学で開催された最終講義には、約200名が参加した。
同大学の専攻名は「官民連携」ではなく「公民連携」である。どちらも同じような意味だろうと筆者は考えていたが、根本教授によると、両者には明らかな違いがある。
「官」と「民」は社会サービスを提供する主体である。一方、「公(公共財)」は目的であり、対になる言葉は「私(私的財)」である。
「官」が「公(公共財)」を提供するために行使している公権力を「民」に移すのが、PFIに代表される単純な「官から民へ」である。しかし、公権力を得た「民」は「公(公共財)」よりも「私(私的財)」(民の収益)を目的に行動するようになる。
これが通常の経済学的な解釈だが、そこに一石を投じるのが「公民連携」の考え方だ。つまり、「民」でも「公(公共財)」を担いうる。その仕組みこそが「公民連携」つまりPPPの役割であるという。
このことから、根本教授はPPPを一言で言うと「官民の役割分担」だと説明する。しかし、これではちょっと分かりにくいので、筆者なりの言葉で翻訳すると、「民的な思考(効率性を重視)で、公(公共財)を提供する」となる。

したがって、公(公共財)の社会性を上げるだけでも、公(公共財)の費用対効果(VFM)を上げるだけでも、民の収益性を上げるだけでもだめ。それらすべてを同時に実現しうる「社会的費用対効果の最大化」がPPPの目的だという。
この目的を達するためには、公権力に競争性を持ち込む必要があるし、民には「公のために」という使命感が求められる。逆も然りで、PPPによって公権力に競争性が持ち込まれ、民は「公のため」という使命感を強く持つようになったとも言えるだろう。
ちなみに同大学の同専攻は、公共政策研究科ではなく「経済学研究科」に置かれている。これも異質に感じる人がいるだろう。なぜ経済学だったのだろう。
公(公共財)を提供する主体は「官」がいい。いやいや、「民」がいい。こうした二者択一は有権者に分かりやすく、とかく政治家の公約になりやすい。しかし、実際はどちらも最適ではなく、その間にある「官民の役割分担」が正解であるが、「どちらでもない」というのはどうしても政治家には好かれないので日の目を見ない。また、PPPの目的が「社会的費用対効果の最大化」であることから、経済学研究科に置いたのだそうだ。これも根本教授の判断だった。
もし「官民連携」専攻と命名していたら、そして、同専攻が公共政策研究科に置かれていたら、日本のPPPはPFIに終始し、今ほど幅広い領域、多様な形態のPPPは広がらなかっただろう。これもまた根本教授の功績である。
根本教授はよく「将来は必ずしも不確実ではない」という。人口減少、少子高齢化はいずれも予測できたし、インフラの老朽化にいたっては100%予測できると強調する。そのうえで、根本教授は講演の最後に後進達にこうメッセージを残した。
「合理的に将来を予見し、対策を考えるには民の知恵が必要であり、それを勇気をもって実行するのは官(公権力)の役割である。公権力をうまく使いこなす人になり、将来の不確実性を減らしてほしい」
(編集長 奥田早希子)