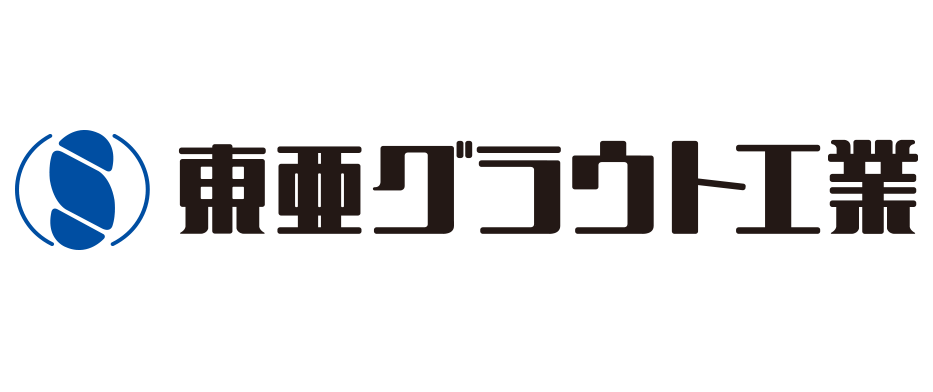水辺にいると、心が落ち着いたり、いつもは話さないようなことをつい話してしまったりするのはなぜなのでしょう?人の心と水の関係について、元・禅僧で現在は「哲学コミュニケーター」として活動する大角康さんに聞いてみました。
『水を還すヒト・コト・モノマガジン「Water-n」』vol.18より転載(発行:一般社団法人Water-n)
「水」は禅僧の生き方のメタファー
「水辺って、なんだかほっとするよね」。確かにその通りなのだけれど、この心の動きに、何か理由はあるのでしょうか?もしかしたら禅の教えにヒントがあるかもしれないと、京都の大角康さんを訪ねました。大角さん、禅において、水にはどんな意味がありますか?
「水は、禅僧にとって生き方のメタファーだと言えます。禅の修行僧は“雲水”と呼ばれます。これは“行雲流水”という禅の言葉からきています。雲が空を流れ、水が川を流れるように、とらわれることなく自由に生きる様子を表していて、禅僧はこの精神を体現する存在だからなのです」
禅における基本的な心の在り方がそもそも水に例えられているんですね! なるほど、さっそく水を考えるヒントになりそうです。
「実際に、水の流れる音を聞いているとすごく心地よく感じますよね。以前、京都のある旅館で、川床※1 での坐禅会を行ったことがあったんです。坐禅とは、姿勢と呼吸を整えることで心の声に素直になっていくことですが、川の流れる音に浸っていると、自分が自然とほぐれていくのを感じました」
確かに、京都だと鴨川の河原でずっとぼーっとしている人もたくさんいますよね。
「ただの水ではなく、流水、つまり水が流れているというのもポイントですね。川はずっと同じように見えても、水は絶えず流れ、変化しています。しかし、水が流れずに一箇所に留まっていたら濁ってしまいます。これを人の動きに例えると、変化することを拒絶している状態なのかなと思います」
変化を嫌い、誰の言うことにも耳を貸さない。そんな感じでしょうか。
「縁」という大きな流れに流されていく
「禅が大切にしているのは、縁にしたがい自分らしく生きることだと思っています。しかし縁に素直にしたがえば、大きく変化せざるを得ない場面に出会うことにもなります。誰しも変化に不安を感じがちですが、そんな時に『大丈夫、なるようにしかならんよ』と、そっと背中を押してくれるのが僕にとっての禅なんです」
物事はすべて流れていくからこそ、今に固執しすぎず、変化を受け入れることが大切なのですね。
「流されるといっても、自分にとって楽なことだけをするとか、長い物に巻かれる、というのは少し違います。禅においては、自己と他者は相互に影響を与え合う、決して切り離せない存在。だからこそ、“自分だけが良ければいい”のでは決してないんです。例えば、不正を強要されて従ってしまうとか、いじめを見て見ぬふりをするとか、他者が苦しんでいることに目を閉じ、そこに加担することは縁に従うこととは異なります」
大変だなと思っても、自分のためだけでなく、他者のためにもより良い行動を選ぶこと、それこそが縁に従って「流される」ということ。そのためには他者とのコミュニケーションが欠かせないですね。
「他者への共感の気持ちは、社会をより良くしたいと考える上で決して忘れていけないものだと思います。自分が社会に発信する際にも、こういう禅の教えが礎にあるのだと思います」
水辺がなぜ心地いいのか、という話から、水と社会の話にもつながっていきましたね。なんだか、これからWater-nを作る上での大きなヒントもいただいた気がします。今日はありがとうございました!
※ 1 京都の夏の風物詩として知られる、川の上や川辺に設けられた席のこと。
大角 康(おおすみ・やすし) Profile
1989年京都府生まれ。「哲学による社会貢献の道を拓く!」をモットーに哲学コミュニケーターとして活動中。人間関係の悩みをきっかけに出家した元・禅僧で、現在は京都大学MBAに在籍。世界哲学会議2028実行委員で、TED×Kyoto University 2025にも登壇。
Instagram: https://www.instagram.com/koukaku0811/