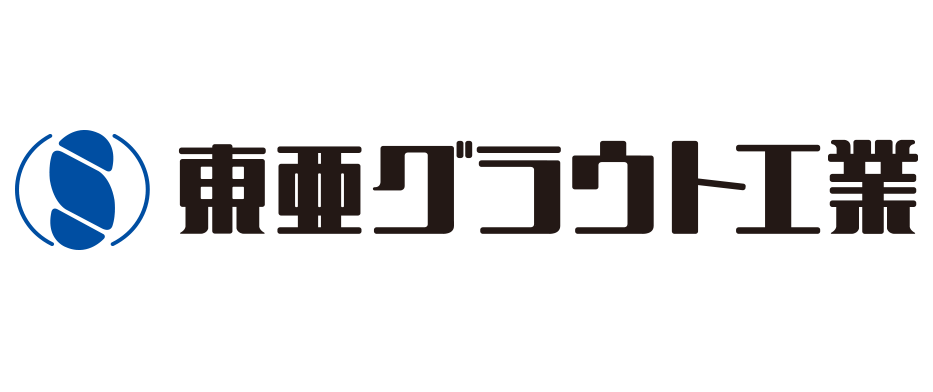いよいよ参院選の投票日、2025年7月20日が明後日に迫ってきました。今回の参院選では、多くの党が公約でインフラの老朽化対策に言及されています。
下水道を半世紀以上も取材してきた筆者としてはうれしい限り。ただ、注目されていることの裏返しとして、それだけインフラの老朽化が進んでおり、このままではインフラを維持できないミライが現実になりそうな危機的状況にあるということです。
明後日、私たちが投じる一票が、上下水道のミライを左右する。そんな非常に重要な局面にあるのですが、一部の公約に含まれる表現が有権者をミスリードするのではないかと危惧しています。それは水道に対して使われている「民営化」という3文字です。
公約の中で、水道の「民営化」に明確に言及しているのは、れいわ新選組と参政党の2党です。次のように書かれています。
■れいわ新選組
いわゆる「水道民営化」(上下水道へのコンセッションなどPFI手法の導入)などは行わず、公営を維持する
■参政党
郵政、水道、NTT、鉄道等の行き過ぎた民営化を見直し、再公営化を進める
いずれも水道の「民営化」には反対で、「公営」には賛成の立場です。では「民営」と「公営」の違いは何でしょう。
すごーくざっくりと、かつ分かりやすく会社に例えて言うと、水道事業を経営している会社があるとして、その社長が民間企業の人なら「民営」、自治体の人なら「公営」ということです。
※自治体のほかに一部事務組合や企業団なども含みますが、分かりやすくするためにここでは自治体と表記します
そういえば、国鉄も郵政も民営化されましたよね。だったら水道の「民営化」だって、ありなんじゃない? そう思うかもしれませんが、実はそうではありません。
また、両党は「民営」でなく「公営」と主張していますが、私たちにはその2つしか選択肢がないのでしょうか。
これから次の6つのステップで、「民営化」がどうミスリードするのか、第3の選択肢はないのかについて解説していきましょう。
- 水道の「民営化」とは?
- なぜ「民営化」に反対するのか?
- 日本では水道の「民営化」はやっていない
- 日本では水道の「民営化」はできない
- だから「再公営化」もできない
- 「民営」でも「公営」でもない第3の選択肢は?
1、民営化とは?
先ほど、水道事業を経営している会社の社長が自治体の人なら「公営」という話をしました。日本では今、99%以上の水道事業が「公営」で運営されています。なぜなら、水道法という法律で「水道事業は、原則として市町村が経営するもの」とされているからです。
それを「民営化」するということですから、今「公営」で運営されている水道事業の社長を、民間企業の人に代えていこうということです。
この時、社長が変わるだけではなく、浄水場や水道管など施設の持ち主も、自治体から民間企業に代わります。難しい言葉で言うと、自治体が持っていた施設の所有権が民間企業に移転されることになります。運営者も自治体から民間企業に代わります。いずれも『5、「民営」でも「公営」でもない第3の選択肢は?』を考える上で、重要なポイントなので付け加えておきます。
「公営」と「民営」、経営者と施設の持ち主、運営者の関係を表にするとこうなります。

※水道事業の社長は正式には「水道事業管理者」と言われています。
2、なぜ「民営化」に反対するのか?
先に述べたように、れいわ新選組と参政党は「民営化」に反対しています。あなたはどうでしょうか?
実は両党だけではなく、水道の「民営化」に反対する人は以前からいました。反対する理由はいくつかありますが、主な理由は水質と料金です。
・命の飲み水の水質が悪化するのではないか
・民間企業は利益を追求するから水道料金が爆上がりするのではないか
仮に水道が「民営化」されたとして、これらの不安は現実になるでしょうか?
まず水質悪化です。これについては国が水道水質基準を定めていますから、たとえ民間企業であっても守らなければなりません。ルールを破れば営業は継続できないでしょう。会社の存続をかけてまで、意図的に水質を悪くする理由があるとは思えません。
そもそも、あなたは「ペットボトル水」を飲んでいませんか? それは民間企業が作った水ですが、同じく民間企業が作った水なのに「水道水」の水質だけ心配ですか? それって不思議ではないですか? 論理的ではないと感じませんか? どうでしょう?
次に水道料金についてです。料金改定には議会の承認を必須にしたり、条例などで値上げの上限を決めておけば爆上がりのリスクは避けられます。
とはいっても、水道が「民営化」されると、自治体の社長(水道事業管理者)は管理者の権限を放棄しなければなりませんから、やはり生活者としては不安ですよね。ペットボトル水とは違い、大量の飲み水と生活用水が万が一にでも止まってしまうと本当に生命の危機ですから。なので日本では水道の「民営化」はやっていませんし、できないようになっています。次からその説明をしていきます。
3、日本では水道の民営化はやっていない
先ほど、日本では今、99%以上の水道事業が「公営」で運営されていると書きました。では残りは「民営」なのかというと、そうではありません。主に地方部の別荘地や団地などの持ち主が協働で管理する水道で、私営水道と呼ばれています。
つまり、日本には「民営」の水道はなく、「民営化」も行われていません。
4、日本では水道の民営化はできない
では、日本では水道の「民営化」はできないのでしょうか。
実は日本でも、かつては「民営化」が可能でした。給水しようとするエリア周辺の「市町村の同意を得た場合に限り」という条件付きではありますが、同意を得れば民間企業も水道を管理運営することが、法律上は可能だったのです。
これでは水道事業が不安定になりかねませんから、2018年に水道法が改正されました。分かりやすく言うと、何がどうなっても社長は自治体の人しか認めないという改正です。
下表を見ると分かっていただけると思いますが、自治体の人しか社長に就くことを認めないということですから、この法改正によって日本では「民営」の水道が不可能になったのです。
5、だから再公営化もできない
先に書いたように、参政党は「郵政、水道、NTT、鉄道等の行き過ぎた民営化を見直し、再公営化を進める」と主張しています。この「再公営化」というのは、「民営化」した水道を、自治体が運営する「公営」に戻そうということです。
ですが、ここまで述べてきたように、日本では「民営」の水道はできず、だから水道の「民営化」もできませんし、「公営」に戻せるような「民営化」された水道事業が存在しません。だから、「再公営化」という表現はふさわしくないのです。
水道の「民営化」という言葉のインパクトは強く、想像以上に生活者の不安を駆り立てるパワーがあります。ですから、「民営化」を阻止して「再公営化」するという言葉には、逆にミライを明るく照らすパワーを感じてしまいます。「民営化」という3文字がもたらすミスリードはここにあります。
また、参政党は「再公営化の動きが世界的に広がっている」とも主張していますが、決してそうではないことがデータで示されています。詳細は「再考・上下水道事業の再公営化」をご覧ください。
繰り返しになりますが、日本では水道の「民営化」はできません。
6、「民営」でも「公営」でもない第3の選択肢は?
れいわ新選組と参政党は、水道は「民営」ではなく「公営」であるべしと主張していますが、私たちにはその2つしか選択肢はないのでしょうか? そんなことはありません。
先に書いたように、「公営」の場合、社長(水道事業管理者)・施設の持ち主(所有権)・運営者という3点セットすべてが自治体です。法改正で社長(水道事業管理者)は自治体にしかできませんが、他の2点セットについては誰が担うかを自由に組み合わせることができます。その組み合わせをまとめたのが下表です。
施設は自治体が所有し、民間企業が運営するパターン、あるいは施設も民間企業が所有して運営もするパターンの2つが考えられます。生産性を高めることが得意な民間企業が運営を担うことで、同じコストでもより質の高いサービスを実現できる可能性があります。
一方、公平性と公正性にたけた自治体が社長(水道事業管理)として民間企業の運営を管理するので、水質や料金に関する住民の不安の解消につなげることができます。
このように自治体と民間企業がそれぞれの得意分野を提供し合い、一緒に水道事業を運営する方法は「官民連携」(PPP:Public Private Partnership)と呼ばれます。中でも施設の所有と運営を民間企業が担う場合は「コンセッション」と呼ばれています。
れいわ新選組の公約には『「いわゆる「水道民営化」(上下水道へのコンセッションなどPFI手法の導入)などは行わず、公営を維持する』と書かれています。しかし、表を見ていただければ一目瞭然ですが、「コンセッション」と「民営化」はまったくことなる運営形態です。
より良いミライを選択するためには、なるべく多くの選択肢があったほうがいい。このことに否と唱える人はいないでしょう。それは水道でも同じはず。「民営」か「公営」かではなく、「官民連携」という第3の選択肢があるはずなのに、すべてひっくるめて「民営化」に集約してしまうと、先に書いたように生活者はその3文字からは不安のパワーを感じてしまう。その結果、第3の選択肢はないも同然になってしまう。ここでもまた、ミスリードが起こってしまうのです。
とはいえ筆者は官民連携を必ず推進すべきとは考えていません。その地域にあった水道の運営方法を、正しい情報を基に地域の人が考え、地域の人が選ぶことが大事です。その結果が「公営」であっても「官民連携」であってもいいと考えています。繰り返しになりますが、その前提として、正しい情報を基に考えていること、そして、より多くの選択肢から賢く選び取ることが大事です。
みなさんは誰に、どの党に投票するか、もう決まりましたか?
決まったという方も、これから考えるという方も、減税や社会福祉など、なんらかの政策に注目して判断されたと思います。この記事が、上下水道などインフラの老朽化対策も含めて考えるきっかけにしていただけることを願っています。(編集長:奥田早希子)