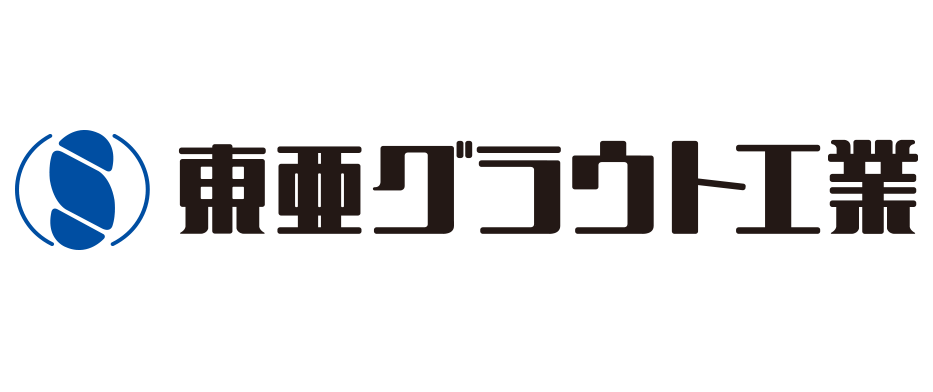老朽化した下水管に起因する道路陥没が相次ぎ、下水道の持続可能性への不安が高まる中、下水道に関連する最新の技術が一堂に会する展示会「下水道展‘25大阪」が7月29日~8月1日にインテックス大阪で開催された。
四半世紀にわたり毎年、この展示会を取材してきたが、これまでは「整備が終わってモノが売れなくなってきたからビジネスモデルを変える必要がある」と言われているにもかからず、相変わらず下水管など「装置」に関する展示が大半だった。しかし、今回は「装置」にこだわってきた従来のビジネスモデルを変革しようとする本気度を感じた。よく言えばそういう表現になるが、別の言い方をすれば、ビジネスモデルを替えざるを得ないほど従来の市場がいよいよ縮小してきたということでもある。
下水道は、下水管や処理場などの整備に莫大な初期投資がかかる装置産業である。そこに属する企業はこれまで、装置を売って利益を得てきた。しかし、整備がいきわたってしまえば、装置が売れなくなるのは当然である。それが今の状況だ。
じゃあ装置の代わりに何を売るのか。今回の下水道展では「下水道事業を売る」という1つの流れが見えた。「下水道事業を売る」というのがどういう意味かというと、「装置を売る」のではなく、「装置を使って生活排水を処理するサービスを売る」ということだ。「モノ売り」から「コト売り」の流れと言い換えることもできる。
「下水道事業を売る」手法としては、自治体が担っている下水道事業を民間企業がマルっと、あるいは一部分を担っていく「官民連携(PPP:Public Private Partnership)」という事業がある。それを提案する企業が明らかに増えた。コンサルもエンジニアリング会社もメーカーも、みんな「官民連携」を打ち出していた。その基幹技術としてDXやクラウドシステムを組み合わせるあたりも似た提案が多くなったと感じた。各社の特徴が薄くなったのは残念ではあるが、一方でコンサル、エンジ会社、メーカーなどの領域を隔てていた境界線も薄くなり、各社がより広い選択肢を持てるようになったことは、よりよいアイデアにつながることでもあるので、一人の生活者としてはうれしい変化である。
もう1つの流れとしては、下水道を利用する生活者を意識する企業が増えたことだ。装置を売っていたこれまでは、各社にとっての顧客は装置を買ってくれる自治体だった。BtoG(government)のビジネスモデルである。しかし、売り物が「下水道事業」というサービスになると、顧客はサービスを利用する生活者になる。これはBtoCである。「下水道事業を売る」というビジネスモデルにかじを切れば、ビジネスモデルをBtoCに転換するのは必然であり、生活者を意識せざるを得ないのは当然である。
売る商品を「装置」から「下水道事業」に変え、ビジネスモデルをBtoCに転換し、生活者のためになるソリューションを提案する。この一連のモデルチェンジで興味深い提案をしていたのは水ingだ。自然災害で上下水道が使えなくなった時を想定し、水のスタートアップであるWOTAの水循環システムなどを活用した住民サポートを提案していた。被災した下水道設備を復旧するという提案はこれまでもあったが、生活者が水回りで困らないように支援するという提案は初めて見た。まさに「装置売り」ではなく「下水道事業(サービス)売り」であり、BtoGではなくBtoCのビジネスモデルである。
当然ながら下水道事業には装置が欠かせない。しかし、生活者目線で見つめ直したら、これまでにない装置やソリューションが見えてくる。そこに新たな市場が生まれるはずだ。
下水道というサービスを売るビジネスモデルを、筆者はこう呼んでいる。
GaaS
Gesuido as a Service
サービスとしての下水道
下水道関係者が下水道を通して暮らしを守っていきたいなら、GaaSへの意識転換、装置売りから事業(サービス)売りへ、BtoGからBtoCへのビジネスモデルチェンジは待ったなしだ。そして、その流れを確固たるものにするために、従来の土木系だけではなく、デジタル、機械、社会科学、公共政策、経営など幅広い領域へとつながりを広げ、人材交流を急ぐ必要がある。(編集長:奥田早希子)