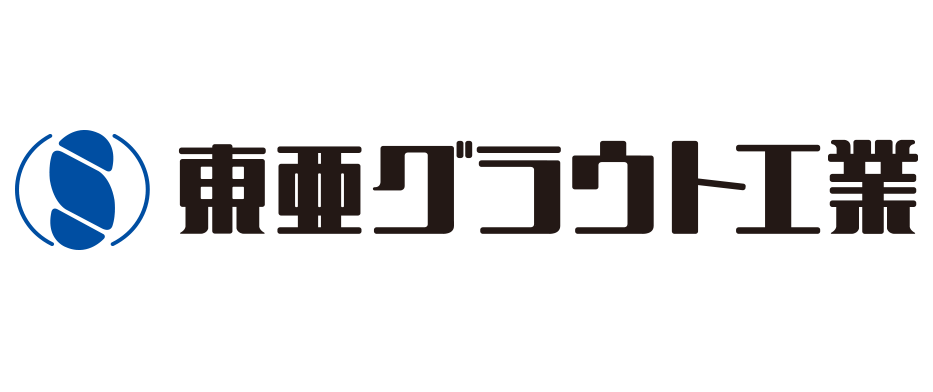人手が足りない、財源が足りない、社会の関心が足りない。
昨今の下水道が置かれている状況は「ないないづくし」です。この状況が長引けば、利用者からはその存在が忘れ去られ、値上げにも反対されてますますヒトもカネも集められなくなり、やがて下水道を運営することができなくなり、下水管などモノは朽ち、まちなかにうんちがあふれる「うんちクライシス」が現実になりかねません。
この最悪のシナリオを回避するために、下水道がもっと魅力的になるための羅針盤として「トキメキの下水道改革(案)」を示したいと思い、3名の業界人に議論していただきました。(企画・進行・執筆:編集長 奥田早希子)
「環境新聞」に掲載された記事をご厚意により転載させていただいています。
紙面はこちらからご覧いただけます→紙面PDF(3MB)
参加者(氏名50音順)

●増山貴明氏
水ing 次世代バリュー創生室室長

●山口乃理夫氏
東亜グラウト工業 社長

●山村寛氏
中央大学理工学部教授

●奥田早希子
Webジャーナル「Mizu Design」編集長
<記事の内容>
私は下水道のここにトキメク
トキメキポイントはここだ!
トキメキの下水道像
「トキメキの下水道改革(案)」はこれだ!
私は下水道のここにトキメク
山村氏 「維持」「持続」にはときめかない
増山氏 下水道が生み出す価値にトキメク
――早速ですがみなさん、「下水道」にときめいてますか? やっぱり仕事のパフォーマンスをあげたり、クリエイティブに新しいアイデアを生み出すには「トキメキ」って必要だと思うんですね。
それなのに、ですよ。今の「下水道界隈」からは、ときめかせてくれるような話が出てこない。下水管などモノは老朽化して、あっちこっちで道路陥没が起きている。それをリニューアルしたくてもカネがない、ヒトもない。カネがないから下水道使用料を値上げしようと思っても、生活者の関心が低いから値上げもできない。「ないないづくし、ないづくし」ですよ。
八潮の事故をきっかけにようやく少しずつ、ちゃんとカネを使って直していこうという機運が高まってきましたが、悪いところを治療するのはマイナスをゼロに戻すだけ。それはもちろん大切なことですが、マイナスからプラスを生み出す創造性がないと、やっぱりときめかない。これでは「下水道の仕事って魅力的!」「下水道で働く人ってカッコイイ!」「下水道で働きたい!」と思う若者は出てこないんじゃないかと思うんですね。
このまま「ないないづくし」が続けば、いずれ下水道処理場は機能を停止し、下水管は朽ち、まちなかにウンチがあふれる「うんちクライシス」が現実になるんじゃないかと、わりと本気で心配しています。
そこで本日は「トキメキ」を基軸に、下水道改革の案を議論していただきたいと思います。まずは自己紹介を兼ねて、みなさんが下水道に感じる「トキメキ」をお聞かせください。まずは山村先生からお願いします。
山村氏 中央大学の山村です。「トキメキ」は私の個人的なテーマで、研究で常に意識しています。
これまで学生に水環境工学や上下水道工学などを教えてきたんですが、日本では水道の普及率が99%近く、下水道を含む排水処理も90%近くあって、ほとんど概成しています。整備の段階はもう終わっているわけです。それなのに、整備のための技術を授業で教えるということに、非常に違和感がありました。
そこで進行役の奥田さんと一緒に、上下水道業界で活躍されている企業の方に話していただく協働講義を8年ほど続けてきました。整備だけではなく、運営のこと、経営のこと、BCP、リスク管理、官民連携、海外展開からESG投資まで幅広いテーマを網羅しています。私自身も学生の立場に立って「上下水道という業界にときめくかどうか」という視点で講義を聞いてきました。

それで感じたことは、確かに上下水道には老朽化や人材不足、財源不足などの危機があって、それを解決するために仕事もたくさんあって、重要な仕事だっていうことはすごい伝わってくるんですけど、誰かが作ったものを維持したり、今あるものをなんとかして次世代につなげるっていう話なんですね。これってどうなんだろうと……。
若者からすると「いやいや、自分たちも新しい未来を作りたいのに、なんで今あるものを維持しないといけないの?」って思う。それってときめかないよな、と感じちゃうところがあります 。
若者を上下水道でときめかせたかったら、例えば2100年に向けてどういう変革を起こすかとか、今と全く違う世界をどう作っていくかとか、思い切って近未来を議論してみればいいんじゃないかと思うんですね。2100年に人口は6000万人くらいまで減りまから、そこで必要な上下水道は、今とは全く違う姿をしているはずです。
すでに近未来で活躍できそうな技術イノベーションは、上下水道の周辺でも起きています。AIの進化、それによる社会の変化は激しいですよね。そういう変化を自ら作り出したい、そして未来を創造したい、それができる企業で働きたいという若者は多いと思います。その思いにこたえられる下水道が「トキメク下水道」ではないでしょうか。
――若者の期待にこたえるという視点が、トキメキへの近道かもしれませんね。では次に山口さんからお願いします。
山口氏 社会人になって34年目を迎えた東亜グラウト工業の山口です。前職は積水化学工業に勤めておりまして、合成木材の営業を8年、経営企画に15年ほど携わり、上下水道業界との関わりと言えばその際にM&Aの案件を手懸けたくらい。ですので私は上下水道の専門家ではなく、東亜グラウト工業に入った10年ほど前から上下水道に深く関わるようになりました。
当社では下水管や水道管のリニューアルなどをやっているので、上下水道業界では水の会社というイメージをお持ちの方が多いと思いますが、上下水道事業の売り上げは単体では半分くらい。ほかに斜面防災や地盤改良、コンクリート構造物のメンテナンスも手掛けています。
テーマである下水道のトキメキについて、まず個人の立場から話します。前職では海外出張が多くていろんな国のトイレを利用してきましたが、先進国であろうと、東南アジアの新興国であろうと、トイレがすぐに詰まっちゃうんですね。先日も仕事でモンゴルに行ったんですけど、都心を少し離れるといまだに穴をあけただけの場所で用を足していました。
ベトナムに積水化学が出資している塩ビ管の製造会社があって、アジアで売上規模がトップクラスくらいなんですが、その工場の前にできた水たまりが、雨が降ってから1週間たっても残っている。排水システムがまったく機能していないんですね。
海外でそうした状況を見た時に、やっぱり日本ってすごいなと感動しました。下水道や排水システムだけではなく、水循環全体のシステムが素晴らしいんですよ。そのトキメキがある一方で、グローバルで勝負できるものを持っているのにできていない状況は、なんだかもったいないなぁとも思いました。
次に下水道で働く人間の立場としてのトキメキを話します。当社は下水管の更生をメインで手掛けているので、工事現場のパトロールによく行きます。学生時代を思い返すと、そうした工事現場にはあまりいいイメージを持っていませんでした。何をやっているのか知らなかったからですよ。
でも管更生の工事現場では、マンホールから資器材や更生用の材料を入れて、車や歩行者の安全にも配慮しながら、道路を掘り起こさずにパイプを再構築している。それを知った時、自分の会社に誇りを持ちました。「こんな素晴らしい技術で社会貢献してるんだ!」って。下水道の仕事は素晴らしいなぁと思いましたよ 。

私が子どもの頃はまだ汲み取り式のトイレを使ったこともあるので、下水道は汲み取りのイメージが強かった。でもこの業界で働くようになって、いろんな最先端の技術が使われていることを知り、ときめいたというか、良いサプライズでした。
――ギャップ萌えでトキメクのかもしれませんね。では最後に増山さんはいかがですか。
増山氏 私は2013年に水ingに入社しました。最初は下水処理場の建設現場に携わり、次にし尿処理施設の降るプラント設計を担当し、その後、PPPの提案営業というキャリアです。また、昨年からは新設された「次世代バリュー創生室」において、採算性と社会貢献を両輪で回せるような取り組みを推進しています。
下水道のトキメキっていうのは、利用者も働く側も下水道のバリューを感じることで生まれるんじゃないかと思うんです。下水道で働く我々にとっては、感謝されて、間接的にトキメクこともある。
じゃあ下水道を使う人は、どこで下水道のバリューを感じるのか。山村先生がおっしゃったように、国内ではほぼほぼ整備されてるので、あって当たり前になっていて平常時はバリューを感じにくい。だから国内では災害時くらいだと思うんですね。
だけど下水道が未整備な途上国に行くと、見方が変わります。都市河川は真っ黒で、水はドロドロしていて、なんか煙まで出ていて、しかも臭い。自然環境の享受ができないし、産業活動に影響がある場合もあるかもしれない。何より、水に起因する衛生面での病気でご家族とか友人を亡くすという、不幸な出来事がまだ起こっている。それを肌で感じて日本に帰ってくると、下水道のバリューを思い起こさせられるんですよ。それをトキメキというのかもしれません 。

働く側の人間としてはそこに、山口社長がおっしゃっていた「誇り」を感じます。それがあるからこそ、この仕事を続けているんじゃないかな。そんな素晴らしい下水道サービスをこれからどう持続させていくか。日本が直面するこの課題に対し、大なり小なり「これは良い解決策だ!」という業務が出来るとトキメクのではと思います。
例えば、下水道それ自体の理解促進や、効果的なPPPや技術イノベーションを進めたり、下水道の集合処理だけに頼らずに分散型とのベストミックスを目指したり。こういった下水道の維持継続に繋がりうる業務にあたるときはトキメキます。「社会課題を解決するために、こんなことをやっているんだ」と言えた時はやっぱりうれしいですね。
さらには、下水汚泥を肥料化するなどの資源循環なども、下水道の本来価値の先の新しい価値を作り出せるので、トキメキがあると思います。
――下水道システムを構成するモノの価値ではなく、モノから生み出される価値にトキメクってことですよね。そのためにモノをうまく使いこなすとか、あるいは今とはまったく別の近未来型の技術を使って同等以上の価値を生み出すとか、あるいは汚水を処理して雨水を排除するという下水道の本来の役割以上の価値が創造されたりしたら、やっぱりトキメキます。
トキメキポイントはここだ!
増山氏 地域に価値を提供していきたい
山口氏 デファクトスタンダードで世界に出る
――それでは次に「トキメキの下水道像」を考えるために、下水道のトキメキポイントを探っていきたいと思います。
山村先生は、今あるモノの維持管理に若者はときめかないとおっしゃっていました。若者だって、いや、若者だからこそ新しい何かを生み出したいんだと。たしかにそういう視点もありますが、維持管理やリニューアルにもAIなど新しい技術を生み出す余地はあるんじゃないですか?
山村氏 確かにそうです。維持管理に若者はときめかないというのは私の仮説なんですね。でもAIならときめいてくれるんじゃないかと思って授業に取り入れたところ、やっぱりそこはトキメキポイントになっていました。
――やはり新しい技術はトキメキポイントになるんですね。
山村氏 なんですが、山口社長と増山さんがおっしゃったように、海外ではまだ下水道が未整備で不衛生な状況にある、日本もかつては同じような状況だったけど今は非常に改善された。我々の世代、つまりひどい状況を知っている世代はそこに下水道で働く意義を感じるんですが、今の学生はいい時代しか知らない。
だから下水道の価値が分からないし、働く意義も分からない。上下水道が重要と言われてもそれが分からないから、持続させる必要性も、維持する必要性も理解できないんです。若者にどう伝えればいいのか、非常にもどかしい。
増山氏 悲しいですが、戦争も起こってみて初めて平和のありがたみが分かる。下水道も事故があったりして初めて、そのありがたみを感じますね。
山村氏 そうなんですよ。事故が起こらないように業界人はがんばっているのに、起こらないと重要性を理解してもらえないのかと……。
山口氏 下水道は広報が下手かもしれませんね。そもそもこの場で「下水道」って語っていること自体が、下水道の魅力を下げている気がするんです。もっといいところにフォーカスしたらどうですか?
例えばメンテナンス。この業界の安定度は抜群ですよ。需要は確実にありますからね。
それから日本ほど少子高齢化が進んでいる国はありませんから、この経験をもって海外に出ていけると思うんです。上下水道では公共事業の予算が減り、やり手も減るわけですが、その苦境にあっても儲かるビジネスモデルを作ることができれば、世界のデファクトスタンダードを取れる。おもしろいと思いませんか? トキメキませんか?
――確かに世界のデファクトスタンダードを取っている日本の下水道って、トキメキますね。GAFAMみたい(笑)
山口氏 当社は将来的には国内の下水道事業では、儲からなくても構わないと考えています。儲けどころは国内モデルの海外展開です。水ingさんなどと一緒になって、オールジャパンで世界に打って出る。そういう夢のある業界だって言いたいです。そのためにはAIなどDX関連の技術は必須ですね。
山村氏 海外で大成功している日本企業はあんまりないですよね? 海外進出を成功させるカギは何でしょう?
増山氏 水道はコスト的にローカル企業に勝てないというのが大きいというのは聞きますね。一方で下水道を含む排水は処理にお金をかける観点が乏しく、垂れ流しになっているところもまだまだあります。
また下水道もいいですが、山間地域の多いアジア、南米などに今更パイプを引っ張って集合処理をするのではなく、浄化槽やし尿集約処理施設も選択肢に入れたほうがいいですよね。これは日本のお家芸だと思います。ロビーイングも含めて現地の企業や政府と協働して、ルール作りからやっていく必要があると思います。
山口氏 ルールを作るという考え方での海外展開には、私も可能性を感じています。ヨーロッパでは組合が強くて、自分たちの雇用に影響する省人化技術の標準化には反対する声が大きいようなんです。日本は逆に省人化モデルを確立しないと事業が成り立たない訳ですから、みんなこぞって省人化モデルの実現に躍起になって取り組んでいるわけです。
いずれ欧米先進国も少子高齢化が進み、日本のようになります。我々は欧米に先立ち、省人化モデルのデファクトスタンダードを作って、将来攻めていけば面白いと思います。
当社では最近、管網解析などができるAIの技術を海外から導入しました。日本 ではそれを使って管路の更新計画を作ったりしているんですが、海外ではそれをBCP的な使い方をするんですね。例えば、八潮のような大規模な陥没事故が起こった場合にどう対策するか。技術や経営などさまざまな立場の専門家の意見を学習させ、AIに答えを出させる。そんな時代になると思います。

山村氏 ヨーロッパと日本ではAIの使い方が違っていて、ヨーロッパではAIを使って上下水道システムを自動運転することは目指していないんです。従業員を守るためという意味もありますが、人口減少を日本ほど深刻に考えていないからのようです。
でも我々はもう直前に人口減少が迫っていて、AIとか、自動運転を取り入れざるを得ない。山口社長がおっしゃるように、それはある意味で日本の強みですね。無人運転までできれば、輸出のチャンスは非常に大きいと思います。
増山氏 下水道の役割は時代によって変遷してきたのでしょうけど、これからはやはり資源循環と脱炭素、さらに言えばにぎわい創出とか、農漁業への貢献も含めて下水道が提供できる価値ってたくさんあるはずなんですね。
あとは中山間地でどのような分散型の水インフラを組み合わせていくか。そこまでやり切っている国は世界の中にはまだない。この部分でも日本がデファクトスタンダードを取れると思います。
――デファクトスタンダードという世界標準のルールを日本が作る。そこには集合処理から分散処理までさまざまな技術や、いろんな人の知見が入っている。世界に先駆けて少子高齢化、インフラの老朽化といったノウハウや経験もみっちり詰まっている。それは海外から見るとトキメキのツールになるかもしれませんね。
トキメキの下水道像
山口氏 観光産業への貢献を考えよう
山村氏 近未来を描き、法制度を整える
――次に「トキメキの下水道像」を探っていきたいと思います。「トキメキの下水道」とはどのような状態、状況のことなのか。それを考えるきっかけとして、先ほど話題に上がった分散型の水インフラを切り口にしたいと思います。
生活用水を得る。生活排水が処理される。その価値を得るための手段は、ネットワーク型の水道や下水道だけではないですよね。浄化槽のような分散型システムだってある。そうやって選択肢が増えることは、生活者にとってトキメキになると思うんです。でも、水道行政と下水道行政は一緒になりましたが、まだ浄化槽は環境省だし、農業集落排水は農林水産省で縦割り行政のまま。これではトキメク未来は描けないと思いませんか?
山村氏 先に話したように、2100年に日本の人口は6000万人に激減します。その状況での上下水道を考えてみたんですが、今あるモノの延長線上にはなく、作り直すくらい抜本的に変えないといけない。
そうなると水道と下水道だけで考えるのはムリがあって、浄化槽はもちろんですが、都市計画とかいろいろな分野の専門家が一緒になって考えていかないといけない。そうすれば、きっと2100年の下水道を示すことができる。ドラえもん的な未来を示す。それが「トキメキの下水道」につながると思います。
――皮肉なことに「トキメキの下水道」は、下水道だけを考えていては行きつかない。いろんな人と一緒に考えることで初めて見えてくるというコトですね。
「トキメキの下水道」が実現する近未来では、法律なんかもガラッと変わっているんでしょうね。
山村氏 そうなんですよ。近未来をイメージして「あれをやりたい」「こうすればいい」と考えていくとですね、その実現を阻害する法律とか制度がいっぱいあることが見えてくる。それを今から変えていったほうがいい。そのためのビジョンが必要だと思います。
――未来のビジョンとして、国交省が「上下水道政策の基本的なあり方検討会」の第1次とりまとめを公表しましたが、どう評価されますか?
山村氏 あのとりまとめの根底にある思想は「持続」と「維持」なんですね。もちろん上下水道経営は持続的であるべきですが、でも規模やシステムについては持続も維持もしなくていいと思っています。国内はコンパクトシティでまとめたり、分散型も取り入れたりしつつ、海外で儲ける。こうした近未来を描き、それを実現するための法律のシステムをちゃんと確立していかないといけません。
山口氏 分散型と言っても昔の汲み取り式のトイレに戻るんじゃなくて、近未来では最新的な技術で家庭内で水を循環利用しているかもしれませんね。そうなれば未来の絵は全く変わります。そうなる可能性はありますよ。
増山氏 私は今、分散型水循環システムのスタートアップであるWOTAという会社にプチ出向してまして、まさに山口社長がおっしゃったような技術の普及に取り組んでいます。技術開発や事業開発を進めているところなんですが、このシステムは現在の法令上、水道でもなければ下水道でもなく、浄化槽でもない。だから普及のためには制度で詰めていくべき要素が多くあるんです。
市町村の全体最適を考えるなら、集約型浄水場と分散型システムの一体設置、一体管理とか。分散型システムを推進する交付金を出すなど、そういう規制緩和なり文化構築なりが進んでほしいです。
――家一棟で完全自立型の水インフラは「トキメキの下水道像」の1つだと感じます。
実は先日、広島県竹原市に行って、WOTAのシステムが設置されたお宅にお邪魔してきました 。あのシステムって見た目がおしゃれでトキメキましたよ。それにユーザーインターフェースがしっかり設計されているから、水処理や機械の知識がない私でも直感的に操作できそう。もはやおしゃれな「家電」ですね。

山村氏 ほんとに「家電」ですよ。とてもいいと思うんですが、下水道とか水道の従来型の補助金は現状では使えないんです。
――そうなんですよね。太陽光もつければ、一軒の家で水道光熱関係のインフラが自己完結できてトキメクんですけど。
山村氏 その可能性は大きいですよ。そうなると、今まで作ってきた上下水道の前提、水質管理や環境管理の考え方の多くを覆さないといけない。でも、それがめちゃくちゃ難しい。
山口氏 市町村の全体最適という観点に立てば、上下水道関係の連携だけではなく、まちづくり全体を考えないといけませんよね。過疎化している地域には豊富な観光資源があることも多いので、積極的に観光と結びつけていく。例えば、そうした地域では積極的に管更生をやるとかですね。
――これまでは都市計画の後追い的に下水道が整備されてきましたが、これからは下水道というか水インフラのあり方に合わせたまちづくりに変えられませんか? 下水道起点のまちづくりに変えていけば、おのずと全体最適なまちになる。それって「トキメキの下水道」じゃないかなと感じています。
増山氏 そうですね。にぎわい創出のポテンシャルはあると思います。トキメキの要素で言うと、下水道による物質や水の輸送機能と集約機能、あと下水処理場の上部などの未利用空間、そして資源含有。これらを組み合わせると、いろんなアイデアが生まれそうです。
事例としてはすでにありますよね。芝浦水再生センターでは立体都市計画制度を用いて上部を商業施設にしていますし、他にも下水汚泥の肥料利用やエネルギー利用も増えています。神戸ではバイオガスで市バスが走っています。
下水処理場を肥料やエネルギーの生産拠点という視点に変えて、例えば処理場内にレストランを作って、処理場内の畑で汚泥肥料で野菜などを育て、それをレストランで食べられるとか。下水処理場を人が集まる魅力がある場所にしてみたい。
山口氏 私もそう思っていたんですが、実は以前に似た取り組みで失敗したことがありまして、下水処理場に人を集めるのはちょっと時間がかかるんじゃないかなと考えるようになりました。それよりも、地域創生や地域再生のカギである観光に対して貢献できる、そんな下水道の仕組みを作っていくことが大事だと思います。
――下水道業界には「下水道を良くするために」って考える人が多いと感じるんですが、私は「下水道で社会に価値を提供するには」って考えたい。その方が楽しくないですか? これもトキメキの1つですよね。
増山氏 下水処理場の運営を含めてマルッと民間に任せて、もっと気軽にPPPができれば、上下水道業界だけじゃなくて、地域にあるいろんな産業とコラボしやすい。そうなれば、社会に価値を提供する下水道になれると思います。そんな仕組みづくりは必要ですね。
山口氏 ウォーターPPPにしても、いかに効率的に維持管理、運営するかばかりで、受益者である一般市民の視点が抜けていると思うんですよ。下水道の経営が効率化されることより、農業ができる、雇用が生まれた、といったことの方が、市民にとっての価値は大きいと思いませんか? ウォーターPPPではどれだけ下水道のコストを低減できたかではなく、そういった点こそ評価してほしいです
山村氏 おっしゃるように地方都市が存続できるかどうか、そのカギは雇用にあると思っています。
地方に必要な多様な雇用を下水道が創っていく。そう考えると下水道に対する考え方や在り方も変わってきます。それらを踏まえてウォーターPPPなどの制度を考え直す必要があると感じますね。
――市民目線での価値創造。これも「トキメキの下水道」のポイントと言えそうですね。
山口氏 フューチャーワークショップって言うんですかね。未来人になったつもりで、将来のまちをどうしたいか、それと一緒にウォーターPPPの在り方を考えていくことが大事なんだと思います。
――やっぱりそうなると上下水道部局だけの話にとどまりませんね。まちづくりの視点、そのためにタテヨコナナメにいろんな主体が融合する。これもまた「トキメキの下水道」のポイントですね。
「トキメキの下水道改革(案)」はこれだ!
山村 「人口6000万人」時代の水インフラを描こう
増山 多業種連携しやすい仕組みづくりを
山口 PPPはコスト削減以外でも評価を
――では次に「トキメキの下水道改革(案)」を考えていきたいと思います。「トキメキの下水道」を実現するために、何をすれば良いのか。
「トキメキの下水道」のポイントの1つに、地域に貢献する姿がありました。地域のなかでも特に山口さんが重視される「観光産業」に対し、下水道はどのような貢献ができそうでしょうか。
山口氏 最近、インフラツーリズムを有料化する自治体が出てきました。1人1万円を超えていても即日完売するツアーもあるようです。日本のインフラを観光でカネに変えるという新しい動きは歓迎で、この動きをもっとしっかりした流れにしていきたい。
というのも、日本の素晴らしいインフラを、外国人観光客が無償で使っていることに、なんとなく納得いかないんですよ。外国人観光客にインフラ税のようなものをお支払いいただくとか、観光地の入場料を日本人より割高にするとか。そこで得た収入をインフラの維持管理に生かす策もありかなと思います。それで観光客が減ることはないですよ。現在訪日外国人は年間4000万人います。一人1万円徴収できたら4000億円になります。大きいと思いませんか?
――下水道がある、そのことがそもそも観光産業に貢献していると考えることができるんですね。そのうえで、その価値を金銭価値に変えることができれば、地方に新たな収入源が生まれるというわけですね。
山村氏 インバウンドで儲かっている、例えばホテルのような業界は下水道の恩恵を大いに享受しているわけですから、下水道に多めに支払っていただいてもいいと思ってました。難しいでしょうけど(笑)
なぜ難しいのか。それはホテル業界が受ける下水道の恩恵を、学術として可視化していないからなんですね。研究者として反省しています。上下水道でも工学的な側面だけではなく、社会的な側面からの研究がもっと必要でしょう。
山口氏 「トキメキの下水道」に改革するには、この業界の給与の改革も必要ではないですか。給料が安いから学生たちに注目されない、という側面はありますよね。ほかのインフラ業界に比べれば一社当たりの売り上げ規模も小さいですし。業界再編は必要ですよ。
当面は下水道の業界は安定しているとか、海外でもデファクトスタンダードを取れるんだとか、社会貢献できるとか、そのあたりをどうアピールできるか。
増山氏 資源循環、官民連携、まちづくりみたいなワードを面接で言う学生が増えましたね。最近はさらにDX、災害復旧がホットワードになっています。この辺りをPRできると会社の魅力を伝えやすいと感じます。
山村氏 この前、業界ですごく頑張っていて安定している会社を学生に紹介したんですが、両親が知らないから行きたくないって言われて、ガクッとしました。
もっと学生と企業との接点を作ったほうがいいですね。先日、とある企業の研究所に学生を連れて行ったんですが、やっぱり現場を見せると関心を持ちますよ。めちゃくちゃ感動してました。トキメキですよ。
小学校では社会科見学で下水処理場に行くこともありますが、中学校や高校の指導要領にも現場見学を必須と書いてほしい。我々は国交省だけじゃなく、文部科学省にもアプローチしないといけません。
とはいえそれでは学生は、言ってみれば受け身で下水道に触れさせられている。そうじゃなくて、主体的にこっちに来てもらうために「宇宙」をテーマにするのはどうですか? 近未来を考えるのと同じですね。月に都市を作るとしたらどんな下水管が必要か、とか考えると楽しいですよね 。
山口氏 宇宙はおもしろいですね。
山村氏 ですよね。だから最近は授業で「宇宙」を使うようにしています。

――宇宙まで考えると、地球の日本での技術イノベーションも加速しそうですね。
山村氏 そこが難しい。2100年、人口6000万人の国を成立させる技術が重要ですが、今を支えている大企業がそこに参加するでしょうか。縮小する都市に投資をするでしょうか。ここは懐疑的です。
おそらく近未来では、大企業の持つ技術やアプローチと、現場ニーズとの間に、ギャップが生じると見ています。そこを埋めるのがスタートアップの新技術です。言ってみればこれからの上下水道には、スタートアップにとってめちゃくちゃたくさんのチャンスが生まれるわけです。
例えばWOTAですね。上下水道業界の顔ぶれが入れ替わる可能性はありますよね。
増山氏 確かにゲームチェンジしたら、プレイヤーもチェンジしますね。
――「トキメキの下水道改革(案)」では、スタートアップ、あるいは既存プレイヤーであってもスタートアップ的発想がカギを握るということでしょうか。
下水道のゲームチェンジが起こると既存プレイヤーは苦しむかもしれませんが、ひとりの生活者としたら、新たなチャレンジができることにときめいて新しいプレイヤーが登場し、結果として幸せに暮らしていけるならそれで構わないですからね。スタートアップにはどんどん水インフラ業界に入ってきてほしいです。でも既存プレイヤーもがんばってほしい!
山口氏 水業界の大企業としてはクボタや積水化学工業がありますが、各社内で見れば水事業は規模は小さい。既存プレイヤーが山村先生が言うギャップに本気でコミットするなら、単独で1兆円くらいの売り上げはほしい。でも、そんな企業は日本にはない。先ほども言ったように業界再編は必要だと思います。
山村氏 上下水道業界の売上規模が小さい理由の一つに、単価の安さがありませんか? パイプにしても、管更生にしても安すぎると思います。
単価が上がらないとヒトが集まらなくて、将来的にパイプ一本すら作れなくなるかもしれません。その時のマイナスのインパクトはめちゃくちゃデカい。業界のPRも大事ですが、その事実をちゃんと伝えないといけないです。
あとはもうちょっと現場にカネが回る仕組みが望ましいですね。
――「トキメキの下水道改革(案)」では、業界再編、適正単価の設定もキーになりそうですね。
それではそろそろまとめに入りたいと思います。山口さんからお願いします。
山口氏 今日は大きく3点についてお話ししました。1点目は国の政策として外国人観光客からインフラ税のようなものをいただいではどうかということ。
2点目はウォーターPPPの評価のポイントです。今はコストを下げることが良しとされていますが、農業への貢献や雇用創出なども評価し、まちづくりや地域創生といった一般市民から見ても実感できる価値創造につなげてく仕組みが欲しいということ。
3点目は、デファクトスタンダードを取って海外市場に展開すること。これまでのODAではコンサルの調査で終わったり、現地企業に発注されて日本の業者が関与できる余地が少なかったですよね。これからはODAに頼らず、例えば水ingさんと当社が組んで、処理場と管路をパッケージにして海外進出する。民間企業は今一度、連携を考えないといけませんし、一方でそんな形での海外進出に関し支援をしてくれる仕組みがあるとうれしいですね。
――増山さんはいかがですか。
増山氏 上下水道行政をもっと開き、縦割りを打破して、多業界とコラボしやすくする仕組みが必要だと感じています。例えば下水処理場の遊休地を活用したいと思っても、今は遊休地利用も入札、目的外使用と言われる、整備費・維持管理費範囲内の収益でなければ補助金返納が必要、上下水道部局にがんばるインセンティブが少ないなど、このような課題が沢山あります。これでは新たなトキメキづくりは進みませんよね。
分散型水循環システムなどの新たな処理に関しても、既存の方法でルール作りがされているので、新たな法制度、財源、活用インセンティブの整理が必要と思います。これができて新たにトキメキを創り上げるスタートアップも活躍しやすくなるんじゃないかと思います。
――では山村先生に最後の締めをお願いします。
山村氏 最近、学生たちによくこういう話をしています。みんなが社会に出てバリバリと働いている2050年頃には、人口減少の影響が顕著になります。そして先ほどから2100年と言っていますが、その頃にはみんなの子どもが20歳になります。その時、日本人が日本に住み続けられているのか、そのためのインフラがちゃんと整っているかどうかは、みんなにかかっているんです。自分の子供が住める日本をどうデザインするか、それを今、考えないといけませんと。
日本をデザインするのは政治家の仕事ですが、政治家任せではだめ。政治家に対して学生も、行政も、学識経験者も、業界も、みんなで議論して、デザインして、方向性を示さないといけません。
これから日本では確実に人口が減ってしまう。その近未来にふさわしいまちやインフラを目指そう、変わっていこうということを、ぜひ業界の人から若い世代に伝えてほしい。
この衰退の方向性のほかにもう1つ、宇宙のような発展の方向性も合わせて、若い世代に未来を見せていく。そうすることで下水道業界は魅力的になり、「トキメキの下水道」になるはずです。
――本日はたくさんのトキメキをいただきありがとうございました。