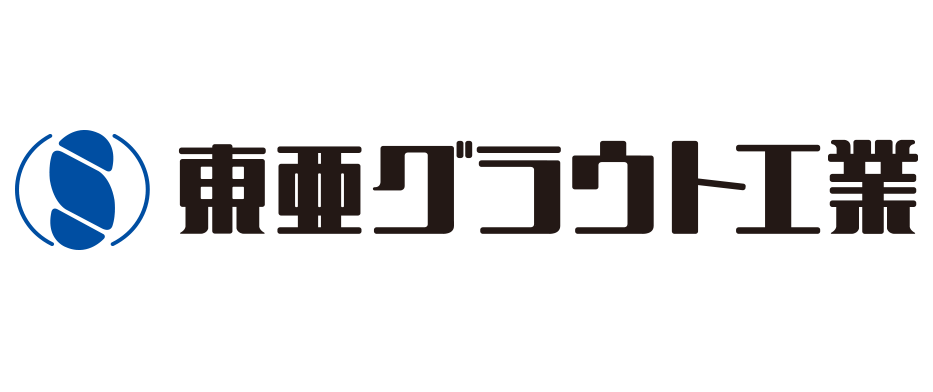下水管の緊急点検で何を調べればよかったのだろうか?
埼玉県八潮市の道路陥没事故の原因が古い下水管だったことから、国土交通省(国交省)は似たような現場を持つ公共団体に緊急点検を要請し、7都府県・13カ所の結果がこのほど公表された。その冒頭の書きっぷりを見て「ああ、この先も道路陥没は防げないな」と感じた。点検すべきものが違うのだ。
2025年2月14日に出された国交省の記者発表資料「埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえた緊急点検結果等を公表します~下水道管路に起因する道路陥没事故の未然防止に向けて~」の冒頭にはこう書かれている。
令和7年1月28 日に発生した埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえ、このような事故の発生を未然に防ぐため、陥没箇所と同様の大規模な下水道管路を対象とした緊急点検と、補完的に路面下空洞調査を実施しましたので、その結果を公表します。(下線は筆者)
つまり、何を点検するか、その対象のメインは下水管で、路面下の空洞調査はサブということになる。でも私はこの優先順位が逆で、八潮市のような道路陥没を起こしたくないのであれば、空洞調査がメイン、下水管の点検をサブにすべきだったと考えている。
八潮市の道路陥没をちょっとでも原因分析してみれば、私がなぜそう考えているかを簡単にご理解いただけると思う。原因分析はフレームワークのひとつで、トラブルの根本的な原因を特定して解決策を導くために用いられる。「原因」と「結果」(トラブル)の因果関係を明らかにできる便利な手法であるが、一方でそれらの設定を間違えれば、効果的な解決策を手繰り寄せることができない。
今回の緊急点検はまさにそれで、「結果」、つまり八潮市で発生した“真の”トラブルが何であったのか、そのトラブルを引き起こした「原因」が何であったのかの最適な設定ができず、もっとも効果的な対応を導けなかったと考えている。どういうことなのかを説明していく。
道路陥没の「原因」と「結果」に間違いはなかっただろうか?
まず、国交省は八潮市の事故で一体、何を「結果」(トラブル)とし、その「原因」を何と設定したのだろうか? 緊急点検のメインの対象を下水管としているので、「原因」は下水管の不具合であり、その「結果」として道路陥没(トラブル)が起こったと想定したのだろう。だからこそ緊急点検をして一刻も早く下水管の不具合を見つけ出そうとしたのだ。そうすることで、道路陥没事故を未然に防ぐことができると考えた。

下水管に不具合があると、必ずではないが道路陥没が発生しやすくはなる。だからこの「原因」と「結果」(トラブル)には、実はある程度の因果関係が成立するから完全に間違えているというわけではない。では何が問題なのかというと、道路陥没と下水管の不具合だけが、「原因」と「結果」(トラブル)ではなかった、その設定が最適ではなかったということだ。
まず「結果」(トラブル)は国交省と同じ「道路陥没」と設定したままにして、「原因」を考えてみよう。あなたなら、道路を陥没させた「原因」は何だと考えるだろうか?
国交省は下水管の不具合が「原因」としているが、果たしてそれがすべてだろうか? 読者の皆様なら、そうではないということがすぐにお分かりになるだろう。道路陥没の“直接的な”「原因」(一次原因)は、地下の空洞である。では、下水管の不具合は何なのかというと、空洞を発生させる原因である。
つまり、道路陥没という「結果」(トラブル)から掘り下げると、まず空洞という「一次原因」あって、その先に下水管の不具合という「二次原因」があるという構造になっている。

このように少し道路陥没の原因分析をするだけでも、国交省が急いで点検した下水管の不具合は、空洞を形成させる原因ではあるが、道路陥没という「結果」(トラブル)を引き起こした直接的な原因(一次原因)ではなく、「二次原因」にすぎないことが分かる。
“緊急”点検というからには「一次原因」である空洞にアプローチする対策が望まれたのだが、一次原因を見落としたか、あるいは適切に設定しなかったからなのか、国交省は二次原因である下水管にアプローチしてしまった。本来であれば「二次原因」である下水管の不具合の点検は、「一次原因」の次でも良かった。この私の考えをご理解いただけるだろうか。
それでもなお、今回はサブであっても空洞調査が行われただけましだった。2015年に下水道法が改正され、腐食しやすい排水設備(下水管など)は5年に1回以上の点検が公共団体に義務付けられたが、調査しているのは下水管の状態だけで、空洞は対象ではない。これではいくら点検しても空洞の発見は遅れ、道路陥没を防止することは難しいと言わざるを得ない。
八潮市の道路陥没の“真”のトラブルを直視しよう
では、どうすれば「一次原因」である空洞にアプローチできるのだろうか? これはそれほど難しく考えることはなく、因果関係のうちの「結果」(トラブル)の設定を変えてみればいい。
これまで述べてきたように、国交省は八潮市では、道路陥没を「結果」(トラブル)と設定した。本当にそうだろうか? 私はそうではなく、“真の”「結果」(トラブル)は、周辺住民の方々が下水道や水道、通信、交通などさまざまな「公共インフラサービス」を享受できず、不自由な暮らしを強いられたことだったと考えている。
両者がどう違うのかというと、前者が下水管の管理者目線であるのに対し、後者は生活者目線であること。このように「結果」(トラブル)を生活者目線で設定し直すことで、「モノ重視思考」から「サービス重視思考」へと発想が転換され、一次原因にアプローチする道が開けると考えている。
「モノ重視思考」というのは、「モノ」そのものに価値を見出す考え方や、そのような考え方に基づく行動のことを勝手にそう呼んでいる。国交省はこちらに当てはまる。これまで下水道というモノを作り、モノを守ってきたのだから当然のことで、八潮市の事故も、下水管というモノに不具合があったから道路が陥没した、モノがちゃんとしていれば道路陥没は避けられた、そう考えた末に、下水管というモノ、つまり二次原因からアプローチする結果になったのだと推察する。
一方の「サービス重視思考」というのは、「モノ」を道具としてとらえ、モノを使って提供されるサービスに価値を見出す考え方や、そのような考え方に基づく行動のことを勝手にそう呼んでいる。「サービス重視思考」的に八潮市の事故をとらえるなら、道路が陥没したから公共インフラサービスが止まった、道路が陥没しなければ不自由な暮らしは強いられなかった、道路陥没したのは地下の空洞が原因だった、そう思考が流れ、道路陥没を引き起こした一次原因である空洞にアプローチするのが当たり前のように感じるのではないだろうか。

道路陥没を繰り返さないために。
インフラも「モノ」から「コト」への流れに、乗ってみる
国交省はこれまで、一所懸命に下水道を作ってきた。下水処理場を建設し、下水管を整備し、維持・修繕してきた。作り、守るべきは下水管などの「モノ」。「モノ」に価値あり。「モノ重視思考」が国交省目線である。そう考えれば、法改正してまで義務化した5年に1回以上の点検も、今回の緊急点検も、下水管という“モノ”が大丈夫かどうかが気になり、空洞という“事象”への対処が苦手としても理解できる。
残念なことに、ここが「サービス重視思考」の筆頭である生活者の視点からかなりずれていると言わざるえない。あなたの家の前の道路の下に、もしかしたら巨大な空洞が空いているかもしれない。そう想定した時、あなたなら「真っ先」に何を点検してほしいと思うだろうか? 私なら、間違いなく空洞だ。下水管はその次でいい。これは私見だが、生活者を代表する意見といってもおおむね間違いはないだろう。
どちらが正しいのかは、その時代によって異なるだろう。下水道を急いで整備しなければならなかった時代は「モノ重視思考」が必要だったことは間違いない。しかし、下水道がおおむね整備し終わった今は、モノの維持管理をしつつ、生活者に下水道サービスを持続的に提供していく「サービス重視思考」が求められるが、まだ切替はうまくいっていないように見受けられる。
今こそ発想を転換すべき時だ。お手本は周りにたくさん転がっている。多くの民間企業が取り組んでいる『「モノ」から「コト」へ』の発想を取り入れるだけでいい(それが難しいのかもしれないが……)。
まずは下水管という「モノ」の維持ではなく、「公共インフラサービス」を止めないことをゴールにする。そうすれば、おのずと何のために、何の、何を点検するのか、優先順位が見えてくるはずだ。
そう考えていくと、道路陥没はもはや「結果」(トラブル)ではなく、公共インフラサービスを停止させる「原因」ということになる。じゃあ道路陥没だけが公共インフラサービスを停止させるのかというと、そんなことはなく、他にもさまざまな原因がある。じゃあそれを回避するために何ができるのか、空洞調査、下水管の修繕のほかにもやれることがあるのではないか、と考えが広がっていく。「サービス重視思考」になると、このように発想が広がり、施策の選択肢を広げることができていいと思う。

さらにそう考えていくと、公共インフラを管理する構造的な問題を解決しなければならないことに気づく。国交省も言及していたが、道路陥没は下水管だけが原因ではない。地盤、地下水位、通行量、降雨量など様々な「原因」が絡み合った「結果」である。「公共インフラサービス」を止めないというゴールを目指すなら、下水道以外の地下インフラの管理者や、道路の管理者はもちろん、気象の専門家などもチームメンバーに必要かもしれない。
今はそれぞれのインフラごとに管理者が異なる「縦割り」組織になっている。全管理者が集まる連絡会を設けている公共団体もあるが、元自治体職員に聞いたところ、そこでやっていることは、頻繁に道路を掘り返さなくて済むように工事スケジュールの調整程度だという。まずはそこで空洞調査のあり方を協議するだけでも意義がある。
さらに「縦割り」を打破するには、地下インフラを統合的に管理する手法が望まれる。新たに組織を設立するという考え方もあるが、そこまでやらなくても、統合的に包括的に民間企業に委託することは有効であり、現実的な方策と考える。
(編集長:奥田早希子)