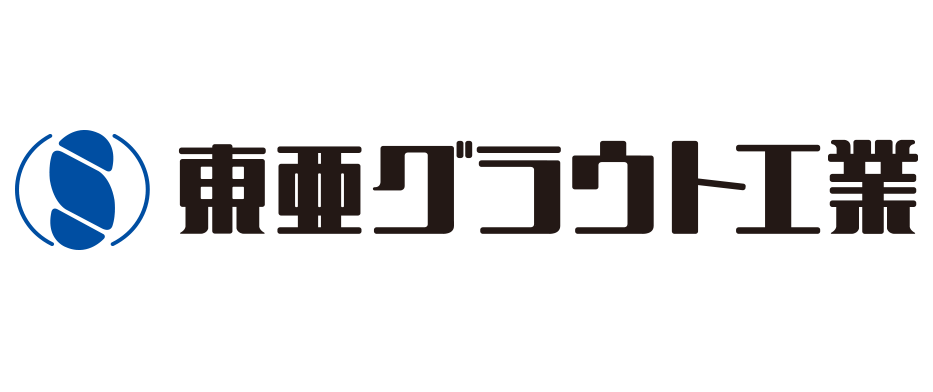清涼な水と肥沃な大地に恵まれ、米どころとして知られる秋田県。そんな秋田県にある国立高等専門学校・秋田工業高等専門学校では、2017年から下水道資源を活用した酒米造りが行われています。この酒米から2023年、日本酒「酔思源」が誕生しました。生徒とともにこのプロジェクトに取り組む秋田高専の増田周平先生に、酒造りを始めた理由について伺いました。

下水再生水は栄養が豊富
下水処理施設では、処理水や汚泥、バイオガスなどが発生しますが、近年ではこれらを「下水道資源」とし、循環型社会のために活用しようという動きが注目されています。そして下水道で処理された再生水もまた、農業に活用するメリットがあるといいます。
「下水再生水は、窒素やリン、カリウムなど植物の生育に必要な栄養を豊富に含みます。しかしこれらを過剰に河川や海に放流すると赤潮のような問題を引き起こすため、下水処理場によっては浄化処理をしてきれいにした水を、さらに高度処理で栄養成分を除去しているんです。有用な成分をわざわざエネルギーを使って除去していることに注目し、この水を農作物の代替肥料として使おうと考えました」(増田先生)

研究結果を学生と飲める
かつて肥溜めを活用して土壌を豊かにしていたように、現代の技術を使って下水道資源を農業に活かす取り組み。その作物として酒米を選んだのはなぜでしょう?
「やはり秋田という土地柄ですね。日本酒造りは秋田が誇る産業ですし、下水道という地域資源の活用を探るなら地域に根づいた産業にしたいと考えました。研究結果を学生たちと飲めるなんて楽しそうですし(笑)」

香り高くフルーティな日本酒に
再生水を活用した酒米栽培は2017年にスタート。模擬水田などでの栽培実験を経て基礎データを蓄積し、安全かつ醸造に適した酒米が栽培できるようになり23年にはついに日本酒『酔思源』が完成しました。
「下水道資源というと、汚いなどのマイナスの印象を持つ人も多いかもしれません。でもお酒を飲んでいただけば分かるように、酔思源は香り高くフルーティで上品なお酒になっていると思います。おいしいお酒を造ることで、下水資源活用の道を広げていけるよう、これからも学生たちと一緒にプライドを持って取り組んでいきたいと思います」


酔思源という名の語源は「水を飲む時には、水源のことを考えなさい」という中国の故事成句「飲水思源」から。現在は秋田県内の一部酒店などで購入が可能。2025年の新酒については秋田清酒のオンラインストアで確認を。
『水を還すヒト・コト・モノマガジン「Water-n」』vol.17より転載(発行:一般社団法人Water-n)