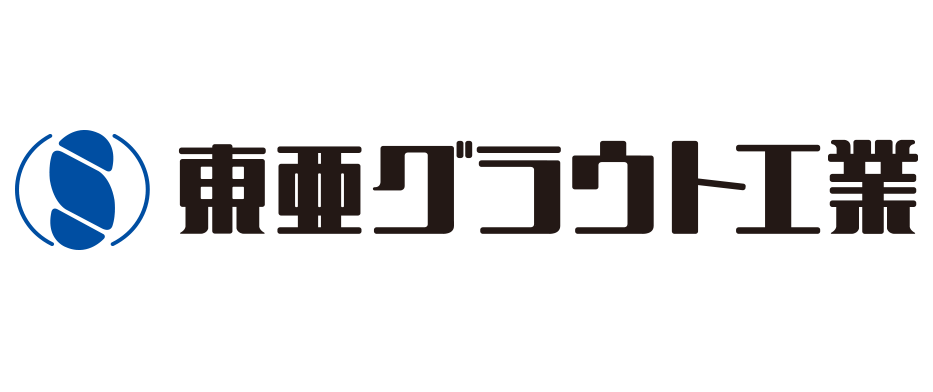佐々木晶二 土地総合研究所専務理事・都市計画協会審議役
既存の建物ストックを活用する再開発事業手法を構想する
市街地再開発事業は、容積率などの規制緩和によって確保できる増床分を売却してそれを事業にあてて、既存の建築物を除却して新しい再開発ビルを建築する事業である。よって、新しい再開発ビルを建築することが前提となっており、既存の建物をリノベーションして活用することは、制度創設時には想定していなかった。
しかし、地方都市の人口減少、経済力の低下を踏まえると、新しいビルを建築するよりも、既存の建物をリノベーションして事務所や商業施設、ホテルなどを誘致する方が、経済性という観点からは現実的である。そして、近年の工事費等の高騰によって、一層、新しいビルを建築することの不利さが際立ってきている。
一方で、市街地再開発事業は、そもそもの目的としては、駅前広場などの公共施設を整備するとともに、従前の老朽化した建物を撤去して火災や地震などからの安全性を向上することを目的としており、この観点からは、地方都市の駅前などで市街地再開発事業を実施する必要性は依然として高いものがある。
そこで、今までは、視野の外に置いていた既存建物のリノベーション自体を市街地再開発事業の一部として位置付け、新しい建物の建築と既存の建物のリノベーション事業を一体として市街地再開発事業として位置付け、適宜従前の権利から新しい建物またはリノベーションした既存の建物への権利返還を認めることを提案する。
このためには、都市再開発法の目的規定や市街地再開発事業の対象地区に指定する高度利用地区で規定されいる都市における「高度利用と都市機能の更新」という概念自体を修正するために、高度利用地区自体の制度変更を検討すべきと考える。具体的には、都市の「高度利用」とは全部の建物を除却して新しく建物を建てるだけに限定せずに、一定の対象地区において、都市計画上、残置して改修を実施する建物と新しく建築する建物が一体として計画的に配置されて整備されることを意味すると定義しなおし、それに伴い必要となる高度利用地区の計画事項の追加を検討する。
さらに、都市再開発法において、再開発ビル(法律では「施設建築物」と呼んでいる)について、施行者が「建築」することに限定せずに、上記の高度利用地区の改正事項に位置付けられた残置すべきと位置付けられた建築物の「大規模な修繕」をも含むように、建築の定義規定を修正することを検討すべきと考える。
その他、必要な法律改正を実施することによって、地方都市での既存の建物のリノベーションと新しいビル建築を一体的に実施する事業を市街地再開発事業として位置付けることが可能となり、市街地再開発事業手法既に整備している、従前地権者に税金がかからなり税制特例や共用部分の整備等に対して行われる補助事業の適用も可能になると考える。
なお、2012年に創設された個別利用区も、既存の建物を活用することを目的としたものであるが、残置できる建物は文化財保護法等の指定を受けるなど建築基準法の適用除外となる極めて狭い範囲の建物に限定されること、既存の建物とその敷地の所有者等は変更されないことが前提となっているなど、活用が難しい点がある。
上記の制度提案は、そのような制約を解消して、柔軟に既存建物のリノベーションと新しい建物の建築を組みあわせて実施することを提案するものであり、地方都市の再開発事業を手がけている民間事業者にヒアリングした結果でも、個別利用区は使ったことがないが、この制度であれば是非使ってみたいというコメントを頂いている。
以上のような、既存建物のリノベーションを市街地再開発事業の中に入れ込むというのは、高度成長期に整備された従来の制度の仕組みからはイメージしにくいが、低成長、人口減少期に突入した現在の日本、特に地方都市にとっては、従来の常識に囚われない新たな発想を実現する事業手法として、制度官庁においても検討すべき価値を有すると考える。
佐々木晶二(ささきしょうじ)
土地総合研究所 専務理事・都市計画協会 審議役
内閣府防災担当官房審議官、民間都市開発推進機構都市センター副所長兼研究理事、国土交通政策総合研究所長、日本災害復興学会理事などを経て現職。被災市街地復興特別措置法立案、津波復興拠点整備事業等復興事業の予算要求立案など。